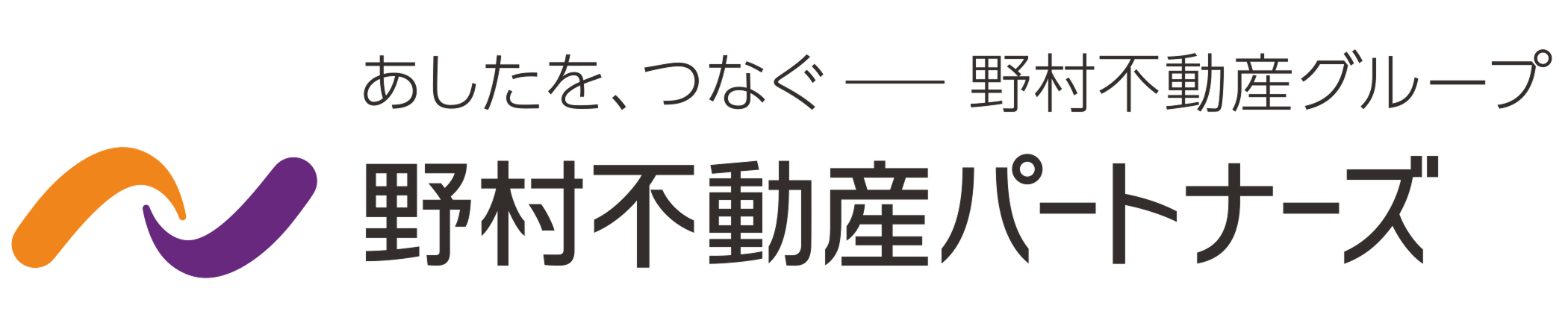“AIと人間の協業”で新人事制度の基盤となるジョブディスクリプションを整備。DX化の成功例を作る
生活関連サービス
1000人以上
- AIアシスタントJD作成
導入企業
| 社名 | ヨネックス株式会社 |
| 従業員数 | 2,633名(連結) |
| コーポレートサイト | https://www.yonex.co.jp/ |
課題と導入効果
| 課題 |
|
| 解決策 |
|
| 導入効果 |
|
ヨネックス株式会社は、「独創の技術と最高の製品で世界に貢献する」をパーパスに掲げ、テニスやバドミントンのラケットをはじめとするスポーツ用品の製造・販売、ゴルフ場の運営などの事業を展開しています。
同社は、グローバル成長戦略の一環として新人事制度に移行し、本社におけるポジションのJDを作成するために「Job-Us」を導入。カスタマーサクセスのサポートのもと、生成AI機能を活用して300ポジションのジョブディスクリプション(以下、JD)を作成しました。
「Job-Us」導入の背景や作成プロセス、今後の展望について、人財開発部の忍田さんと佐伯さんにお話を伺いました。
JDを「誰がどうやって作るか」が課題に

新人事制度導入プロジェクトを統括している、人財開発部 部長 忍田麻衣子さん
―まず、人事制度を刷新するに至った背景を教えてください。
忍田さん:当社は、パーパス「独創の技術と最高の製品で世界に貢献する」とミッション「スポーツと人、人と人をつなぎ、よりよい未来を創造する」の実現に向け、「グローバル成長戦略(Global Growth Strategy : GGS)」を全社で推進しています。その一環として、グローバル人財の確保や社員のモチベーション向上を目指し、2024年10月、従来の年功序列型の人事制度から、パフォーマンス・カルチャーの醸成を重視する新人事制度に移行しました。
新人事制度では、各ポジションの役割を明確に定め、役割に応じた等級を設定しています。この等級に基づいて評価を行い、評価と報酬が連動する仕組みです。年齢や勤続年数にとらわれず、社員一人ひとりが最大限にパフォーマンスを発揮できる環境を整え、「世界のお客様のために楽しみながら競い合う」というスポーツマンシップに基づく企業文化の創出を目指しています。
―新人事制度において、なぜJDの作成が必要になったのでしょうか?
忍田さん:理由は大きく2つあります。1つは社員が自分の役割をよく理解し、目標を立て、主体的に働けるようにするため。もう1つは、新しい評価・報酬制度と連動させ、JDを基準に客観的かつ公平・透明な評価を行うためです。ほかにも、採用活動や社員のキャリア形成、昇格・異動、社内公募、組織理解など、幅広く活用されることを想定しています。
―JD作成にあたり、どのような課題があったのでしょうか?
忍田さん:当社は国内外に多くの拠点を持ち、本社だけでも数多くのJDを作成する必要がありました。人財開発部の限られたリソースで、これだけの数を誰がどうやって作成するかが大きな課題でした。
2024年1月から新人事制度の準備を開始し、10月には運用開始が決まっていたため、時間の余裕もなく……。さらに、多くの 社員がJDのことを知らない状況でゼロから作成しなければならない難しさもありました。人財開発部だけではとても対応しきれないので、外部専門家の協力を得ることにし、「Job-Us」にたどり着きました。
―さまざまな選択肢がある中から「Job-Us」を選んだ理由を教えていただけますか?
忍田さん:一番は、AIに強みを持つ先進的な企業と組むことに、意義と面白さを感じたからです。当社は日本の伝統的な企業で、AI活用やDXの導入はまだこれからという段階。そのため、人財開発部のミッションを「人財戦略でイノベーションを起こし、多様な人財と組織の力を最大化する」と定めており、イノベーションを常に意識し、新しい技術や手法を積極的に取り入れて、組織と人財を成長させたいという強い思いがあります。
AIを活用したJD作成プロジェクトは、社内に新風をもたらす良いきっかけになると考えました。もちろん、AI活用によって工数の削減や高いコストパフォーマンスを実現している点も大きなポイントでした。
AIと人間の協業で、300ポジションものJDを作成

―「Job-Us」の導入後、JDの作成はスムーズに進みましたか?
忍田さん:基本となる300ポジションのJDを期限までに作成することができました。通常であれば多くのメンバーが動員され、現場の社員もヒアリングや内容の調整に多くの時間と労力を割かれるはずでした。
しかし、「Job-Us」の導入によって今回は私たち2名で対応でき、現場社員の負担も最小限で済みました。AIで工数を大幅に削減できたことに加え、Job-Usカスタマーサクセスチームにサポートしてもらえたおかげです。今後、ほかのポジション向けにJDを展開する際は、基本の300ポジションの中から近いものを複製・調整することで、迅速な対応が可能になると見込んでいます。

JD作成のプロジェクトをリードした 、人財開発部 HRコーディネーション課 課長 佐伯理奈さん
―JD作成の具体的な流れを簡単に教えていただけますか?
佐伯さん:まず、各部門長にアンケートを実施して、業務に関する情報を収集しました。その後、集めた情報と部門ごとのパーパス&ミッションや等級定義などをAIにインプットし、AIでJDのドラフトを作成。このドラフトをもとに、各部門長にヒアリングを行って内容を調整し、最後に人財開発部が細部を整え、最終確認を行って完了しました。
ドラフトの作成や各部門長へのヒアリングは、Job-Usカスタマーサクセスチームにお任せし、アウトプットに対して私たちがフィードバックする形で進めました。
忍田さん:AIとJob-Usカスタマーサクセスチーム、そして私たちが協力して作り上げたという感じですね。人間の手でしっかりと事前準備を行い、AIが作ったものを最終的に人間が補完する という、まさに「AIと人間の協業」によって、非常に効率よく進めることができたかと。
佐伯さん:これをもし、自分たちだけでやっていたら……想像するだけで怖いですね(笑)。
―できあがったJDを見て、どのような印象を持ちましたか?
忍田さん:AIのクオリティーの高さに驚きました。現場の社員がゼロから作成すると、どうしても主観的な内容になりやすく、表現も人によってバラつきが出てしまいます。その点、AIが客観的に提案した標準的なポジション定義をもとに調整することで、一定の質を確保することができました。コンピテンシーやスキルも事前に設定したリストから選択するので、表現を統一できたのも良かった点です。
また、会社全体だけでなく、「部門ごとのパーパス&ミッションも盛り込みたい」という私たちのこだわりも反映でき、ヨネックスらしいJDに仕上がったと満足しています。効率性、成果物の質、コストを考えると、費用対効果の面からも非常に良い結果となりました。
社員の理解も深まり、今後のJD活用の基盤ができた

―「Job-Us」を導入し、ほかにも何か良い影響はありましたか?
佐伯さん:JDに対する社員の理解が進んだように感じます 。最初は「JDを作る」と言われても漠然としていて、それがどういうものでなぜ必要なのか、想像できない社員が多かったんです。しかし、実際にJDのドラフトを見せてからは「これからのヨネックスに必要だと思う」と前向きな反応が増えました。完成形をイメージできるドラフトがあったことで、JDの重要性が伝わりやすくなったのはとても良かったです。
忍田さん:議論を進める上でも、ドラフトがあるのとないのとでは大違いだったと思います。形があるものに対しては「ここはいい」「ここを変えたい」などと意見を言いやすいですから。ドラフト提示後は社員からも活発に意見が上がるようになり、進行がスムーズになりました。何もない状態では議論が進まないので、AIで早々にドラフトを作って見せるというのは効果的だと思います。
―「Job-Us」で特に役立った機能は何ですか?
佐伯さん:AI生成機能には、AIのすごさを改めて実感させられました。「ゼロ」から作り上げるのは非常にエネルギーが要るので、AIが5割でも6割でも作ってくれるのはもう、本当に助かりましたね。何もないところから、みんなで頭を悩ませながら作ることに比べたら、AIの提案を修正する方が圧倒的に楽ですから。
それからもう1つ良かったと思うのは、AIが提案する一般的なJDを見て、社員が「他社ではどうなのか」と他社の取り組みに目を向けるようになり、AIの提案を積極的に取り入れる姿勢も見られたことです。ともすれば自社視点にとらわれがちな中で、社員が客観的な視点を持ち、各ポジションが果たすべき本来の役割や自社の強みを再確認できたのも、AIで作成した効果だと思います。
忍田さん:今回のプロジェクトを通じて、AIを活用すればより効率的に、より高い成果を生み出せることを実感できました。そしてJDだけでなく、社内でAI活用の成功事例を作れたことも、ヨネックスの今後の成長につながる大きな成果だと考えています。
―最後に、今後の展望をお聞かせください。
忍田さん:今後は、国内外の拠点にもJDの作成と運用を展開していく予定です。その数は今回の倍以上にのぼる見込みで、もろもろ整理は必要ですが、基盤ができているのでスムーズに進められると考えています。
そして、この先何よりも重要なのは、JDをしっかりと運用し、「全社員が必ず使うツール」として根付かせること。「作ったけど使われなかった」とならないように、人財開発部が継続的に社内へ発信し、「楽しみながら競い合う」企業文化を大きく進化させていきたいです。
※掲載内容は、2024年10月の取材当時のものです。