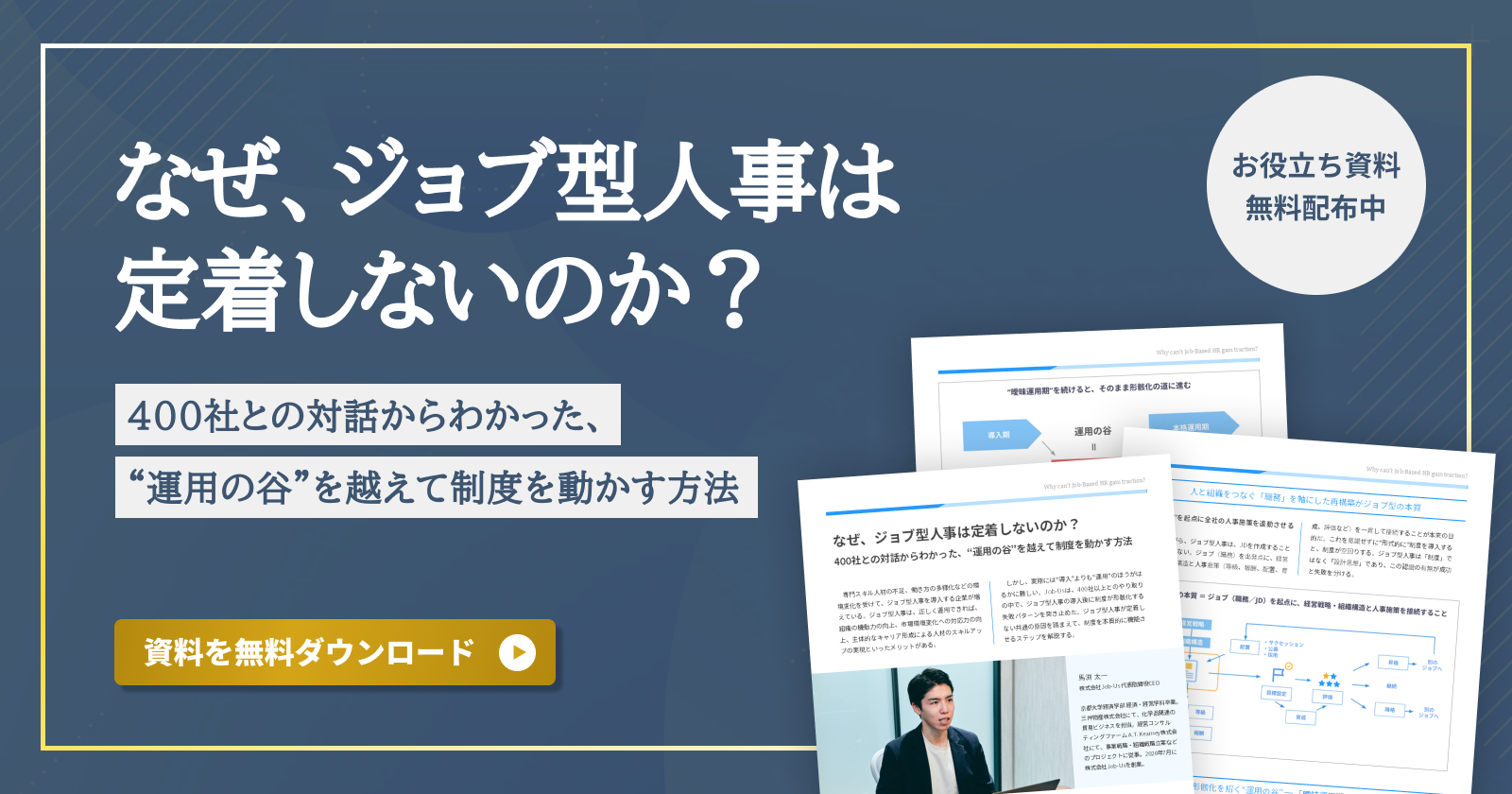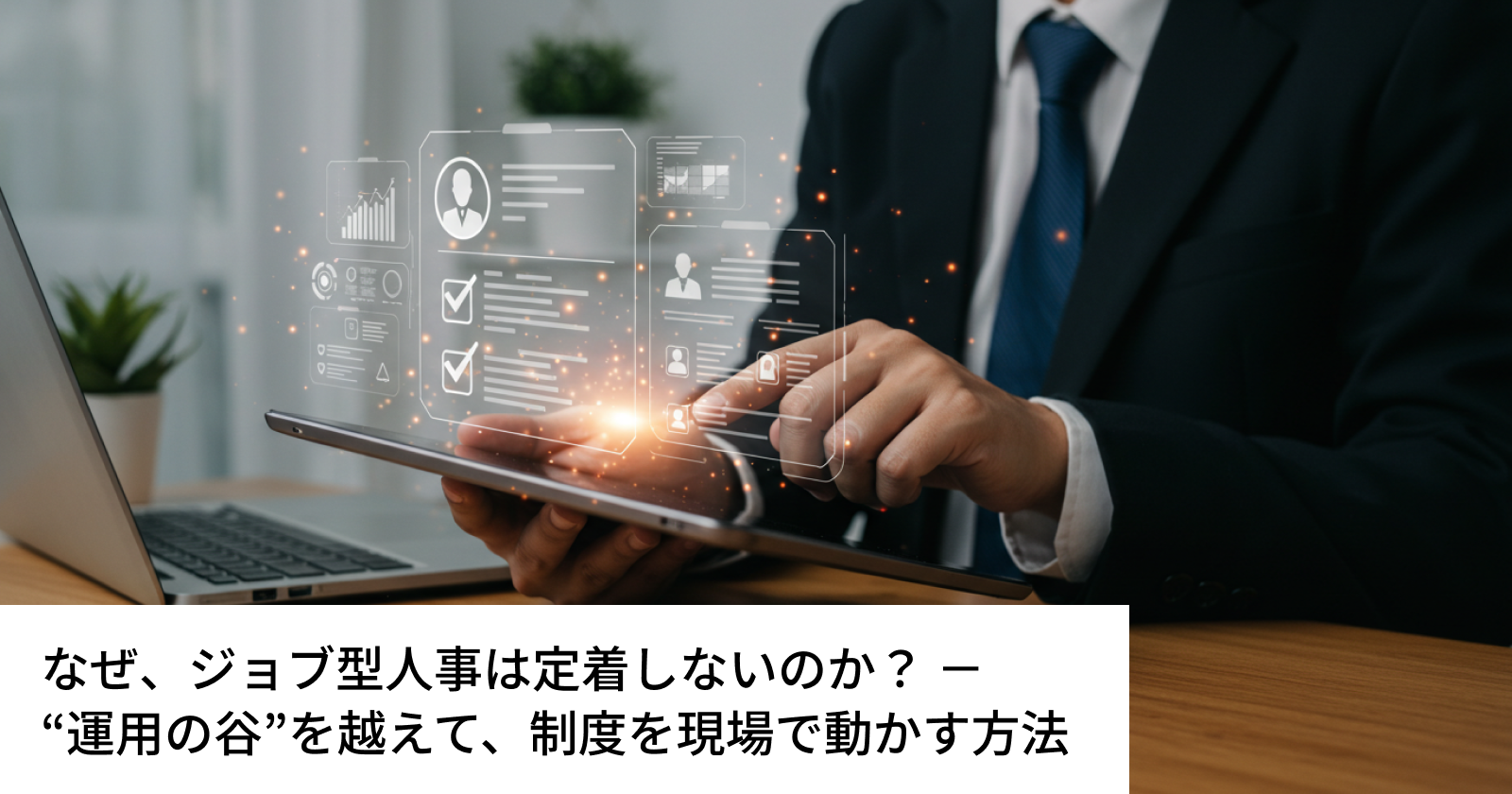ジョブ型人事
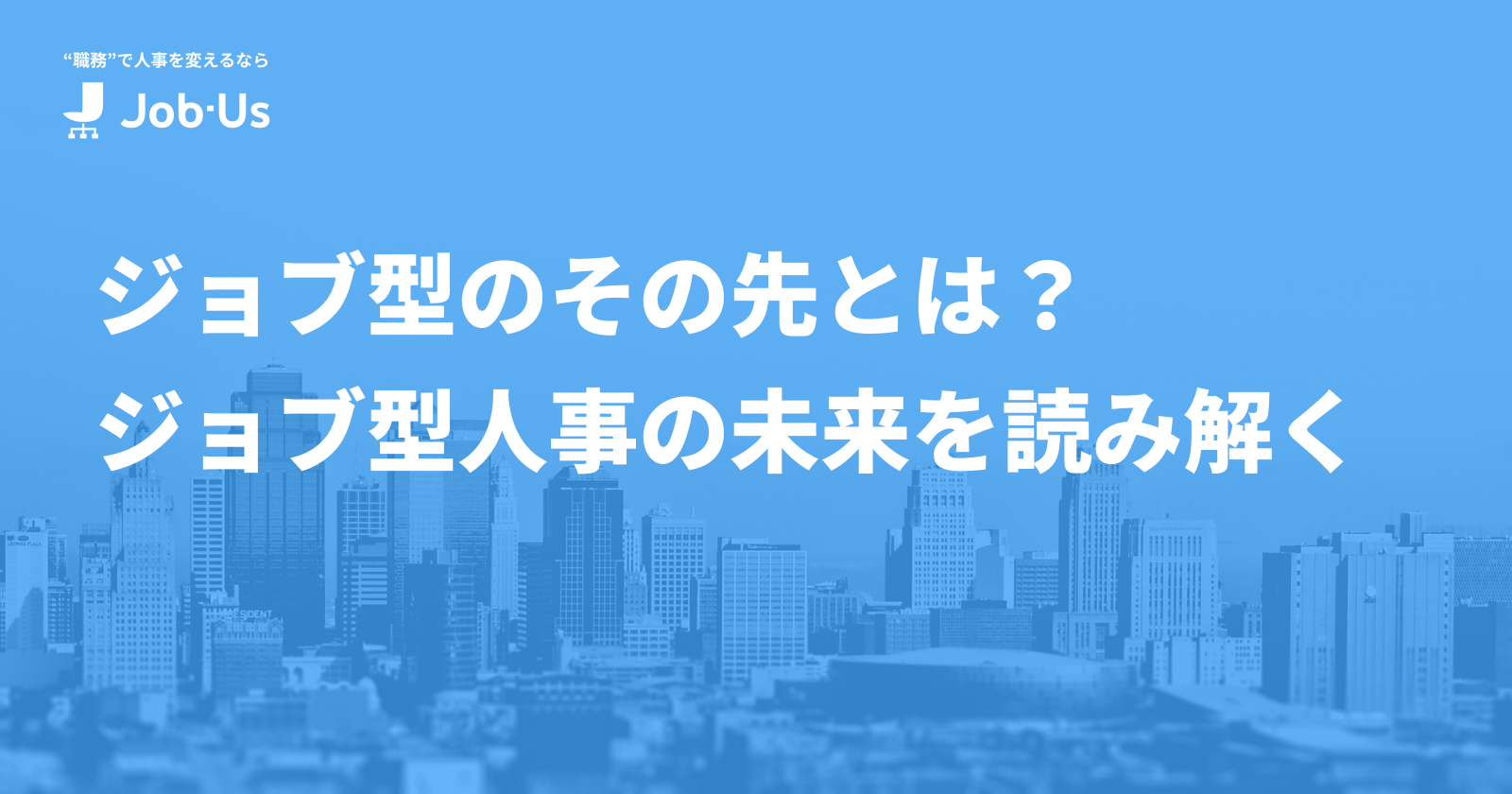
ジョブ型のその先とは?有識者のコメントから読み解くジョブ型人事の未来
「ジョブ型」という言葉が日本で浸透して2年以上が経過しました。
最近では、ジョブ型のその先・未来についても、レポートや講演などで議論がなされています。
この記事では、いくつかのレポート・講演から読み解けるジョブ型の進化形に関してまとめていきます。
目次
ジョブ型の未来に関する有識者の見解
デロイトトーマツ「”ジョブ”ではなく”スキル”が意思決定のベースに」
デロイトトーマツの「デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド2023」では、「ジョブ型の終焉」と伝え、下記のようにコメントをしています。
ジョブの終焉への先導:
ジョブとジョブを区別し、タスクをグループ化し、労働者を狭い役割と責任に分類していた境界線は、現在、イノベーションや機敏性等の組織の成果を制限しています。多くの組織が労働力に関する意思決定のベースラインとして、ジョブではなくスキルを使用することを試みています。労働者はジョブから解放されると、組織や労働者の成果の向上に向けて、その能力、経験、興味をより活用していく機会を得られます。
デロイト・グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド2023
デロイトトーマツによれば、ジョブ型の未来では、組織の意思決定において「ジョブ」ではなく「スキル」を使用するということになります。
仕事の未来×組織の未来 フォーラム「人事戦略はポートフォリオベースになる」
マーサー ジャパンが主催した、2023年3月開催の「仕事の未来×組織の未来」(How to reboot your organization’s work operating system)というフォーラムでは、企業の雇用や人事戦略は「ジョブ型」から「ポートフォリオベース」に推移すると伝えています。講演会ではポイントとして下記が述べられています。
- 雇用や人事戦略に関して、一人の人が複数の仕事を組み合わせて働く『ポートフォリオベース』の考え方が導入され、アジャイル(迅速に仕事に対応できる)なスキルを持つ人材が求められるようになっていく
- (1)ジョブではなく、ジョブを細分化した仕事(タスクやスキル)をポートフォリオベースで考え、(2)細分化した仕事でプラットフォームを構築し、(3)細分化した仕事を最適につなげる方法を考える
仕事の未来×組織の未来フォーラムでは、ジョブ型の未来では、「ジョブ」ではなく、ジョブを細分化した「仕事」すなわち「タスク」や「スキル」を組み合わせていく、ポートフォリオベースの考え方が導入されていくと伝えています。
PwC「事業戦略とリアルタイムで連動するジョブ型3.0へ」
2023年4月に発表されたPwCの「ジョブ型人材マネジメントサーベイ 2022」では、「ジョブ型3.0」へ進化している、と述べています。
ジョブ型3.0とは具体的に下記の内容を指しています。
「ジョブ型3.0」はそこからさらなる進化をしたものとして、事業戦略との連動(中長期的な視野+リアルタイム性)、職務情報と人材情報の高度な連携(職務単位に職務・人材適合度を定量的に把握)、それらを運用するための柔軟かつ体系的な推進基盤を具備したジョブ型人材マネジメントを指します。
PwCによれば、職務情報と人材情報の高度な連携(職務ごとに職務と人材のマッチ度を定量化する)が未来のジョブ型になる、としています。
なぜ、職務とスキルのマッチを重視するのか?
ジョブ型が今後どうなっていくのか、その未来については、各社の見解は異なっているようにも見えます。
しかし、共通しているのは、ジョブの中のRole and Responsibilities(具体的な職務内容と責任)の部分・スキル部分を、社員のスキルや適合度などを参考にマッチさせる、というポイントになっています。
「職務」をきっちりと定めて、それに人材を当てはめていくような職務を厳格に運用していく方法ではなく、職務で定義するスキルと人材のスキルのマッチングを重視する方向です。
これは近年注目され始めている「スキルベース」のような考え方になりますが、なぜスキルとのマッチングを重視するのでしょうか?
Job-Us Labo編集部の見解は以下の4点です。
①ジョブディスクリプションによる業務の制限を排除するため
従来のジョブ型では、ジョブディスクリプション(JD / 職務記述書)を作成し、社員に対して職務範囲を制限していました。
しかし、それが浸透しすぎると、社員は与えられたミッションに対しては業務を全うしようと動きますが、その範囲外のことに対しては積極的に行わなくなってきます。組織や会社の方向性が変わり、求めるジョブの内容が変わった場合は、その都度ジョブディスクリプションを書き換え、社員に説明する必要が出てしまいます。
流動性が高く、変化の激しい環境において、そのような運用は難しくなっているということが理由の1つと言えます。
②イノベーションを促進するため
スキル型を導入した場合、バックグラウンドが異なっても、求めるスキルやそれに近しいスキルを有している人に、業務を任せやすくなります。
例えば、営業管理として、顧客の売上推移や見込みデータの分析・管理に従事しているAさんという社員がいると仮定します。このAさんは、データ分析に長けており、かつ顧客の意見をくみ取ることが得意であるため、データスキルや現場の声を活かしてマーケティング業務に携わってもらう、といった任用も柔軟に可能になります。
その場合、営業管理というマーケティングとは異なるバックグラウンドを持つ方がマーケティング部門に加わることになります。
これまでのマーケティング部門にはなかったような視点や考え方が入るため、新たなイノベーションが生まれる可能性も高まるでしょう。
③個人のキャリアアップを促進するため
ジョブ型で運用をする際に、会社が必要な組織やポジション(職務)を作成した場合、上位のポジションに空きが出ない限り原則的には昇格ができません。その会社で働き続けた際のキャリアアップに閉塞感が出てきていまいます。
一方で、スキルをベースに運用するケースや、職務の一部のみをベースに運用するケースでは、従来のジョブ型と比較して社内でのキャリア構築が実施しやすくなります。
将来のキャリアパスが描きやすく、社内で閉塞感が出てくるのも防げるでしょう。
④社内のデータ基盤を構築するため
ここ数年、workdayやSuccess Factors、SmartHRなど、人事のクラウド管理システムが急速に発展しています。
こうした背景の中で、社員の過去の経歴や強み・弱み、有しているスキルなども管理ができるようになっています。
その結果、職務とスキルのマッチングを行うことも現実的になっており、スキルベースのような考え方での人事施策の実行がも実現可能になってきたのだと推測します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「職務」をベースに忠実に運用していくような従来の厳格なジョブ型は、徐々に変わっていくのかもしれません。
とはいえ、スキルをベースにした人事の場合でも、スキルを定義するために「職務」を定義することが欠かせません。
その意味で、職務の重要性は変わらないのではないでしょうか?