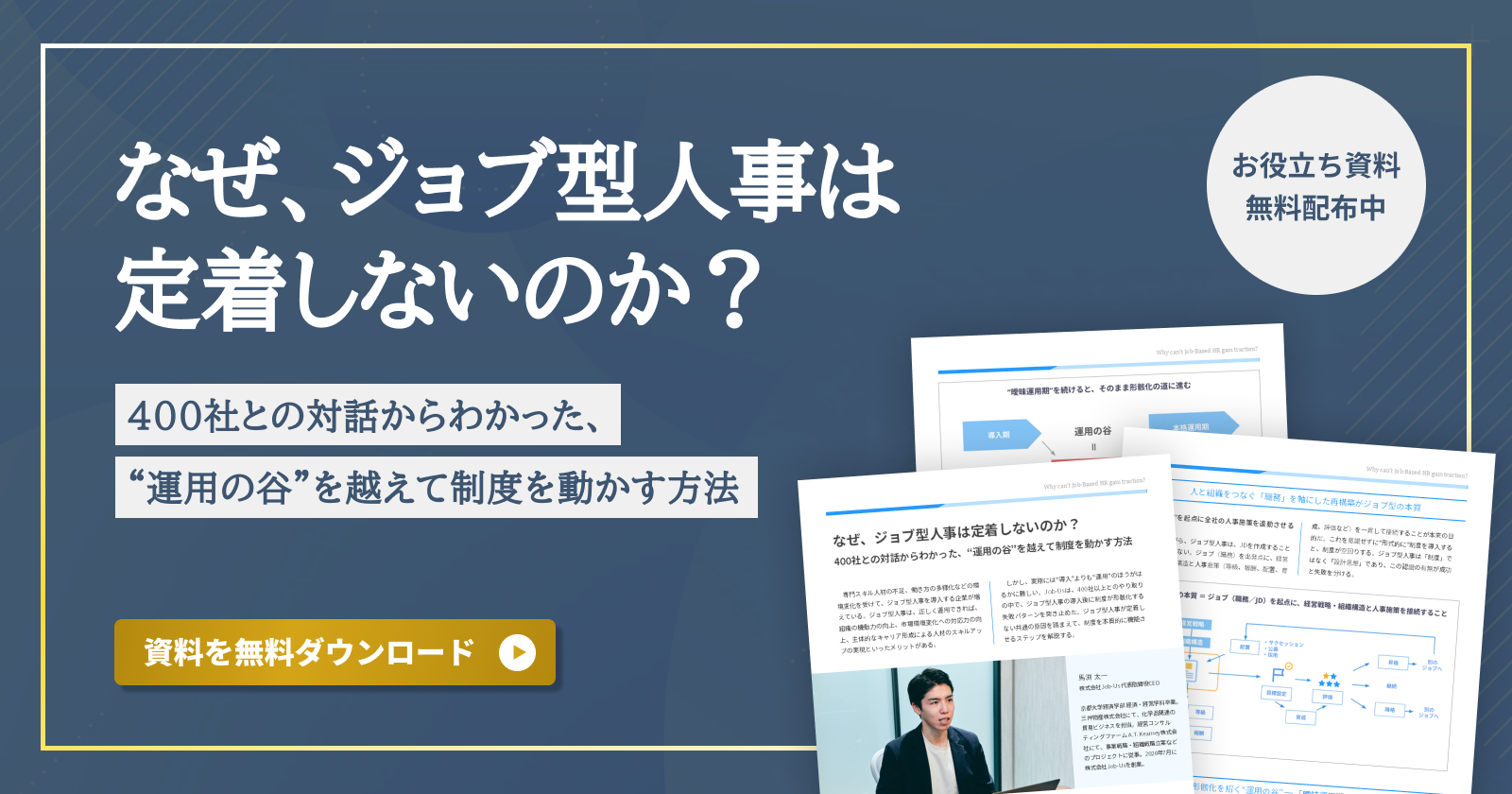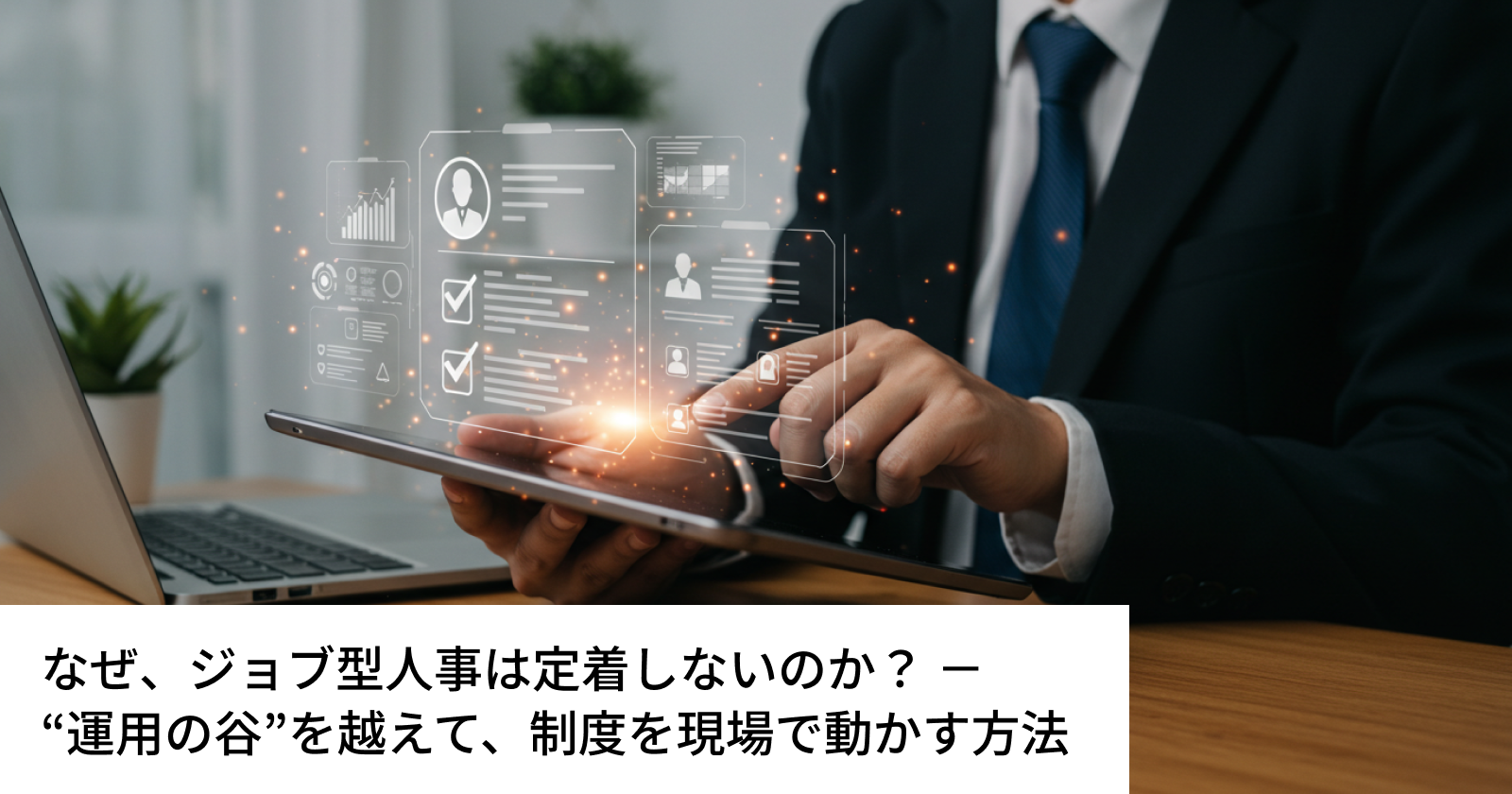ジョブ型人事
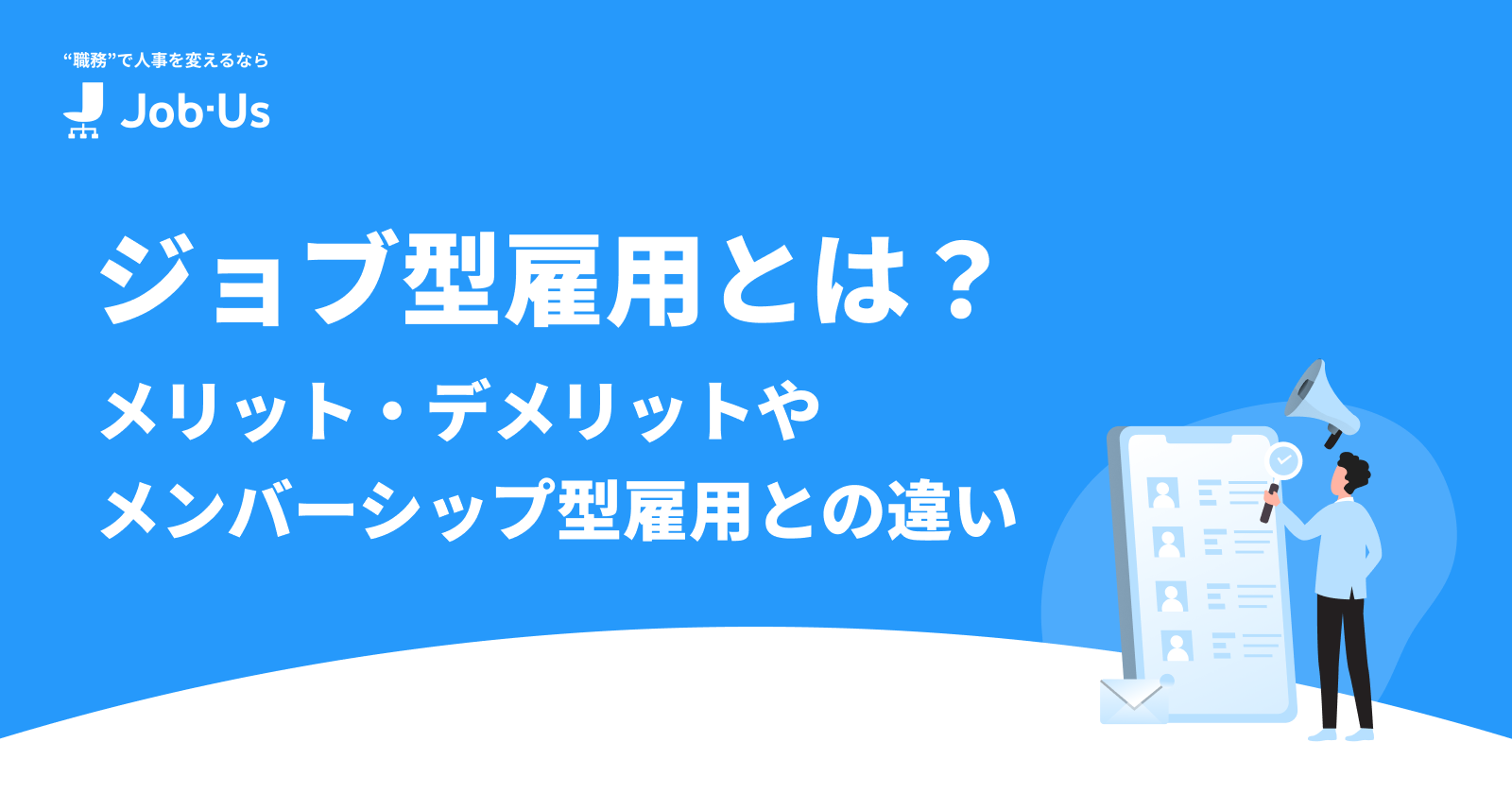
ジョブ型雇用とは?メリット・デメリットやメンバーシップ型雇用との違いを解説
ジョブ型雇用への注目が高まっています。職務内容や必要スキルを明確にし、その職務に適した人材を採用・配置するこの雇用形態は、グローバル化や専門性の高まりを背景に、富士通、ENEOSホールディングス、日立製作所など多くの大手企業で導入が進んでいます。一方で、導入にはいくつかの注意点もあります。
本記事では、ジョブ型雇用とは何か、そのメリットとデメリット、従来のメンバーシップ型雇用との違い、導入の手順や注意点、そして大手企業の事例を詳しく解説します。ジョブ型雇用の導入を検討している企業はもちろん、働き方の多様化に関心のある方にもおすすめの内容です。
目次
ジョブ型雇用とは?

ジョブ型雇用とは、人事制度の1つで、ジョブディスクリプションに基づく「ジョブ(職務)」を軸に、その役割・ポジションにふさわしいスキルや経験などを有する人材を雇う仕組みです。言わば、該当の職務のエキスパート人材を採用・育成する雇用形態といえます。「ジョブ型雇用」は、労働政策研究・研修機構(JILPT)労働政策研究所長の濱口桂一郎氏によって命名されたと言われています。
2020年3月に経団連が公表した「採用と大学教育の未来に関する 産学協議会・報告書 Society 5.0 に向けた大学教育と 採用に関する考え方」においては、ジョブ型雇用を「特定のポストに空きが生じた際にその職務(ジョブ)・役割を遂行できる能力や資格のある人材を社外から獲得、あるいは社内で公募する雇用形態のこと」と定義しています。加えて、「ジョブ型」は、「当該業務等の遂行に必要な知識や能力を有する社員を配置・異動して活躍してもらう専門業務型・プロフェッショナル型に近い雇用区分であり、欧米型のように、特定の仕事・業務やポストが不要となった場合に雇用自体がなくなるものではない」と補足しています。
ジョブ型雇用は、主に欧米企業では一般的な雇用方法ですが、日本企業の大多数は採用後に職務を割り当てる「メンバーシップ型雇用」を採用してきました。しかしながら、ITスキルを持つ専門性の高い人材の不足、外国人雇用の増加、リモートワークの浸透、転職市場の活性化などを背景に、最近では大企業を中心にジョブ型雇用の導入が進んでいます。さらに、同じ仕事なら同じ待遇が求められる「同一労働同一賃金」の導入もジョブ型雇用の促進を後押ししています。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い
日本の雇用方法の主流はメンバーシップ型雇用です。メンバーシップ型雇用では、企業が必要とする人材の「数」を採用し、その後に職務や勤務地をそれぞれに当てはめていきます。原則として、就業規則や雇用契約等の内容は全て同一となります。特に新卒採用に関しては、日本国内のほとんどの企業がメンバーシップ型雇用を採用しています。総合職での一括採用のケースなどがイメージしやすいでしょう。
一方で、ジョブ型雇用は日本でも中途採用では多く導入されています。その他の相違点としては、以下のような点が挙げられます。
【ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の主な違い】
| ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |
| 対象 | 主に中途採用者に適用される
(新卒採用で適用されるケースは少ない) |
主に新卒採用者に適用される |
| 職務・ポジション | 募集・採用の段階で決まっている | 採用決定後、各人員に職務を割り当てる |
| 給与・報酬 | 職務内容や等級、ポジションに対して報酬が連動 | 業務の遂行能力に応じた報酬 |
| 人事評価 | 職務・ポジションに連動した評価を行うため、客観性が高い | 評価基準を平準化することが難しく、相対的に主観性が残る |
| 育成 | スペシャリストの育成に向いている | ゼネラリストの育成に向いている |
| キャリアパス | 必要な経験やスキルが開示されるため、明確な指針を持ちやすい | 業務内容が特定領域に絞られないため、幅広い業務を経験できる |
| 雇用契約 | 職務単位での雇用となるため職務がなくなった場合、契約内容によっては解雇の対象になりやすい | 終身雇用制度、年功序列が基本で担当業務が変えながら長期雇用されやすい |
ジョブ型雇用と成果主義の違い
ジョブ型雇用と混同されやすい概念として「成果主義」が挙げられます。業務内容に報酬や待遇、役職が連動している点においてジョブ型雇用と成果主義はよく似ています。どちらも同じ制度と誤解される場合がありますが、ジョブ型雇用の命名者である濱口桂一郎氏は「ジョブ型は成果主義ではない」と明確に述べています。
ジョブ型雇用は、特定の業務(職務・ジョブ)があり、それを遂行できる人材を採用・育成します。この場合、対象の職務・ジョブを遂行できる人材かどうかは採用の段階で評価済みであり、報酬も職務内容に応じてあらかじめジョブディスクリプション(職務記述書 / JD)で定められています。したがって、職務を遂行した際の報酬は確定しています。仮に想定以上の成果や結果を出したとしても、それが報酬や待遇に反映されるかどうかは、雇用方法ではなく評価制度によって決まります。
ジョブ型雇用においては、採用後は担当の職務を遂行できているかがチェックされ、業務の品質や成果にかかわらず、報酬が一律となる点が特徴です。
一方で、成果主義はその人の業務品質や成果の良し悪しに応じて報酬を決定する評価制度の一つです。ジョブ型雇用で特定業務の遂行のために人材を採用した場合でも、メンバーシップ型雇用でまず人材を採用をしたのちに業務を割り当てた場合でも、いずれにおいても適用ができます。
ただし、担当する職務が明確に定義されるジョブ型雇用の方が幅広い業務を担うメンバーシップ型雇用よりも成果が見えやすく、成果主義との相性が良いと言えます。
ジョブ型雇用が注目される理由

近年、ジョブ型雇用が注目を集めている背景について、深掘りしていきましょう。なぜジョブ型雇用が注目されているのか、理由や背景を解説していきます。
2020年に経団連によりジョブ型雇用が提言されたため
ジョブ型雇用が注目されるようになったきっかけの一つに、2020年に日本経済団体連合会(経団連)が発表した「2020年版 経営労働政策特別委員会報告」があると指摘されています。
この報告書で経団連は、日本型雇用システムを「メンバーシップ型」と位置づけ、そのメリットを活かしつつも適宜ジョブ型雇用を導入していくべきだと提言しました。この提言が、雇用形態の見直しの機運を高めたと考えられます。
専門スキルを持つ人材が不足しているため
市場環境変化のスピードが上がり、ビジネスのグローバル化が進むにつれて、ますます高い専門性が必要となっています。こういった環境に素早く適応し、国際競争力を高めるためには、ITスキルやデジタルスキルを始めとする専門性の高いスキルを持つ人材を確保することが不可欠です。
このようなビジネス環境に適した人材を獲得するために、ジョブディスクリプションを用いて必要となるスキルや経験を明確化し、業務内容を限定した上で、採用活動を強化する動きが活発になっています。特定の職務に特化したスペシャリストを採用できることがジョブ型雇用の導入が進む背景の一つと言えます。
働き方の多様化やダイバーシティ経営が推進されているため
急速に進むグローバル化や少子高齢化による労働人口の減少により、多くの企業で多様な人材の獲得、多様な働き方の推進が必要となってきています。外国人の雇用や育児・介護による時短勤務など、多様な働き方が促進されています。
企業側としては、ジョブディスクリプションにより勤務時間や勤務地などを限定することで、様々な形での人材の雇用が可能になります。多様な価値観や個々の事情に対応できるジョブ型雇用は、人材の有効活用につながるのです。一方、働き手側においても、様々な働き方を選択できるジョブ型雇用の方が多様なニーズを満たすことが可能です。
終身雇用が限界を迎えているため
これまで日本で長く定着してきた終身雇用は、右肩上がりの経済成長を前提として制度となっていました。しかし、VUCAの時代において経済の先行きが不透明な状況が続く中、人件費やその他コストが圧迫するリスクを抱える終身雇用は、制度の維持が難しくなってきています。
年功序列による優秀な若い人材のモチベーション低下や離職、組織の新陳代謝の低下・硬直化などを防ぐためにも、終身雇用からジョブ型雇用への移行する企業が出てきています。
リモートワークや在宅勤務の浸透
リモートワークや在宅勤務の導入により、対面でのコミュニケーションや気軽に相談できる機会が減少したことで、目標や業務内容が不明瞭になりやすくなったことも背景の一つと考えられます。コミュニケーションの頻度が低下する中でも業務成果を生み出すために、各従業員に求められる職務内容や目標を明確にするジョブ型雇用のメリットが大きくなっています。
大手企業によるジョブ型雇用の導入
富士通、ENEOSホールディングス、日立製作所など大手企業のジョブ型雇用の導入が進んでいることも背景の一つとして挙げられます。大企業の動向には注目しているビジネスパーソンも多く、有名企業のジョブ型雇用導入に関するニュースが相次いで報道されたため、経営者や人事責任者を中心に「ジョブ型」を意識するきっかけとなりました。様々な企業がジョブ型導入に踏み切っており、具体的な導入の事例については後ほどご説明します。
ジョブ型雇用のメリットとデメリット|企業側

ジョブ型雇用の導入は、企業側と従業員側のそれぞれにメリットとデメリットがあります。まずは、企業側の観点からメリットとデメリットについて説明します。
メリット①:自社のニーズに適した人材を採用できる
ジョブ型雇用では、ジョブディスクリプションを用いて職務内容と必要なスキルを明確にした上で求人募集を実施します。定義される職務は企業側の要望・ニーズが反映された内容になり、応募者もそれを理解した上でエントリーします。そのため、自社のニーズに沿う求める人材を的確に採用できる可能性が高まることがメリットの一つです。
ただし、ジョブディスクリプションで定義する職務内容があいまいな状態だとミスマッチが発生してしまいます。職務(ジョブ)を明確に定義し、募集する人材の要件や業務内容が的確に伝わるようにすることが重要です。
メリット②:スペシャリスト人材を獲得できる
ジョブ型雇用では、企業が求める特定のスキルや経験を有する人材を募集するため、特定領域に専門性を有するスペシャリスト人材を獲得できることがメリットです。特定の自社課題や特定のプロジェクトなどに最適な専門人材を獲得できる可能性が高くなります。
ジョブディスクリプションで定義している基準以上のスキルや経験を持つ即戦力人材であるため、採用後の研修や教育などのコストを最小限に抑えられると言えます。短期間での成果創出や生産性の向上などにもつながりやすいでしょう。
メリット③:職務に連動する公平性の高い評価が可能
ジョブ型雇用では、あらかじめ記載されたジョブディスクリプション、評価基準、給与体系などに同意した人材を雇用することになり、採用の段階で評価や報酬の基準が決まっています。そのため、上司や評価者の主観的な認識に左右されることがなく、明確で客観性が高く公正な評価が可能となる点がメリットです。
デメリット①:人事制度に抜本的な変更が必要になる
従来のメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用では、評価の基準や項目、報酬の内容、勤務地、ジョブローテーションなど人事の幅広い項目が異なっています。これからジョブ型雇用を導入する場合には、そういった人事制度や人事領域の設計を根本的に見直す必要性が出てきます。
また、ジョブ型雇用を適用した従業員を新規で採用する際は、従来から在籍している従業員に対して誤解が生じないよう、丁寧な社内説明が必須になります。
デメリット②:柔軟な対応が難しくなる
あらかじめ業務内容や範囲などが明確に定義されるジョブ型雇用では、定義される職務内容・範囲を超えた業務は基本的に行いません。社内の他の部署で人材が不足した場合でも、ジョブ型雇用で採用している人材を異動させたり、ジョブローテーションを行うことが困難になります。柔軟な人材配置などが難しくなる点がデメリットです。
場合によっては、早期退職につながってしまうことも考えられます。
デメリット③:ゼネラリストが育ちにくい
ジョブ型雇用では、業務内容などがあらかじめ定められているため、特定領域に特化した人材が育つ一方で、幅広い業務を経験するゼネラリストタイプの人材は育ちにくくなります。特定領域だけに強い専門人材ばかりになると、組織の柔軟性が失われるリスクもあります。
ジョブ型雇用のメリットとデメリット|従業員側

次に、従業員側の観点からジョブ型雇用のメリットとデメリットについて説明します。
メリット①:スキルアップにつながりキャリアパスが明確になる
ジョブ型雇用では、自身が力を発揮しやすい領域の業務に専念できます。自分の得意分野をさらに深めることができるため、その分野に関する経験やスキル、知識がますます深まっていきます。ジョブ型雇用は、各ポジション・職務に必要とされるスキルや経験が開示されるため、将来具体的に何を学んでいけばよいか、どんな経験を積んだらよいかが明確になるため、スキルアップの指針が明確です。そのため、自分がどういったキャリアパスを描くのかイメージしやすくなるでしょう。
メリット②:成果を上げやすい環境になる
ジョブ型雇用では、職務が定義され必要とされる経験やスキルが明示されているため、応募者側も自身が最も得意としている領域、成果を生み出しやすいポジションに応募ができます。また、業務範囲が明確で自分の仕事に集中できるため、成果を上げやすいと言われています。
デメリット①スキルアップには自己研鑽が不可欠
上記のメリットでご説明したように、ジョブ型雇用にはスキルアップがしやすいという側面があるものの、スキルアップのための各種研修の提供や教育を実施することはあまり多くありません。メンバーシップ型雇用ではある程度受動的でもスキルアップの場が用意されてきましたが、ジョブ型雇用では自身が主体的に目的を持った自己啓発が必要です。
企業側の制度や環境に過度な期待をせず、自らの意思で学び続けることが大切です。
デメリット②:雇用契約によっては解雇のリスクが高まる
ジョブ型雇用の企業側のデメリットとして、柔軟な人材配置が困難であることをご説明しました。これを従業員側に置き換えると、該当の職務・ポジションがクローズないしは不要になった場合は、その職務に就く人材も不要になるということを指します。したがって、雇用契約の内容によっては、メンバーシップ型雇用よりも解雇のリスクが高いと言えます。
特にエンジニアは、プロジェクト単位でジョブ型が適用される場合があるため、雇用契約の内容を事前によく確認しておくことが重要です。
ジョブ型雇用の導入手順

ジョブ型雇用の導入は以下の手順で進めていきましょう。
- ジョブ型雇用の適用範囲を検討する
- ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成する
- 職務評価を行う
- 等級を設定する
- ジョブディスクリプションを定期的に見直す
それぞれの手順について説明します。
1. ジョブ型雇用の適用範囲の検討
まず、ジョブ型雇用をどの範囲まで適用するのかを検討します。メンバーシップ型雇用からいきなりすべての職務・ポジションをジョブ型雇用に切り替えることは困難です。ジョブ型雇用が適していない業務が存在する場合もあり、ジョブローテーションを頻繁に行う業務などの対象者からは不満の声や反発が生じる可能性があります。
現在、社内にあるすべての職務・ポジションを棚卸しして分析した上で、配置転換が発生しない部署や職務を中心に段階的にジョブ型雇用の導入を検討しましょう。
2. ジョブディスクリプションの作成
ジョブ型雇用の適用範囲を決めたら、ジョブディスクリプション(職務記述書)を作成します。ジョブディスクリプションとは、ジョブ(職務内容)に関する詳細が記載されている文書のことです。職務内容、業務範囲、必要なスキル、求められる成果などが記載されます。日本語では「職務記述書」と訳され、Job Descriptionの頭文字をとって「JD」と略称で呼ばれることもあります。
ジョブディスクリプションの作成は、以下の手順で進めていきます。
- ステップ1
- 経営・事業戦略と組織ごとに求められる役割を理解する
- ステップ2
- 組織内の各ポジションの役割と責任範囲を明確化する
- ステップ3
- 実際にジョブディスクリプションを作成する
具体的な作成方法はこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください。
3. 職務評価の実施
ジョブディスクリプションの作成が完了したら、職務評価を行います。職務評価とは、ジョブディスクリプションをもとに職務のレベルを判定するプロセスです。厚生労働省では、職務評価の手法として以下の4つを推奨しています。
| 職務評価の手法 | 内容 |
| 単純比較法 | 自社の職務を比較し、職務の大きさを評価します。職務を細かく分解するのではなく、全体として捉えた上で、どちらの職務の方が大きいのかを比較します。 |
| 分類法 | 作成した職務レベル定義書をもとに職務の大きさを評価します。 |
| 要素比較法 | 職務定義書をもとに、職務の要素を洗い出します。近い要素を持った職務ごとに要素を比較することにより、職務のレベルを評価します。 |
| 要素別点数法 | 要素比較法と同様に、職務を構成する要素別に評価します。職務を比較するのではなく、要素ごとに点数をつけることにより、職務のレベルを評価します。 |
参考:厚生労働省「多様な働き方の実現応援サイト 職務評価の手法」
4. 等級の設定
職務評価が完了したら、等級を設定します。職務評価で判定した職務レベルをもとに、職務価値をいくつかの等級に分けていきます。等級は人事評価や報酬と連動する前提のもと、設計することが重要です。等級の分類が細かすぎると評価に時間がかかってしまい、逆に粗すぎると報酬レンジや評価との連動性を保つことが難しくなります。自社の報酬設定も加味しながら、適切な等級区分を検討しましょう。
等級を区分した後、各等級ごとに報酬を設定していきます。ジョブ型雇用ではジョブ・職務に対して報酬が連動するため、採用活動時のポジションの魅力度や採用後の従業員のモチベーションに影響する非常に重要な要素です。
他社と職務内容が変わらないにもかかわらず、報酬が見劣りしている場合は、他社への転職リスクが生まれます。人材の流出を防ぐ意味でも、同業他社の相場を意識しておくことが重要です。
5. ジョブディスクリプションの定期的な見直し
等級の設計までが完了すれば、ジョブ型雇用を導入できる段階になります。ただし、ジョブディスクリプションで定義する職務の内容は、経営方針や人事戦略の変化、市場環境の変化等に合わせて、変化していくものになります。業務内容が実態とずれているにもかかわらず、その職務を定義しているジョブディスクリプションが変更されない場合、ジョブ型雇用の運用が形骸化してしまいます。
ジョブ型雇用を有効なものにするためにも、定期的にジョブディスクリプションや職務評価を見直すことが重要です。主に以下のタイミングで見直し、実態に即した運用を心がけましょう。
- 組織再編のタイミング
- 異動のタイミング
- 半年または一年ごとの定期見直し
- 中期経営計画策定のタイミング
ジョブ型雇用の導入時の注意点

ジョブ型雇用の導入時には、注意すべきポイントが2つ挙げられます。
- 職務情報を抜粋して求人情報にも記載する
- 従業員へ職務の役割や評価基準を明確に伝える
ここでは、それぞれのポイントについて説明します。
職務情報を抜粋して求人情報にも記載する
ジョブ型雇用の導入時には、必要なスキルや業務内容などの職務情報をジョブディスクリプションに記載するだけでなく、採用ページの求人情報にも詳しく掲載することが重要です。雇用している従業員はジョブディスクリプションを見ることができますが、求職者や応募者は直接見ることができません。
具体的で明確なジョブディスクリプションを作成しても、求人情報にその内容が記載されていなければ、自社のニーズに沿った人材はエントリーをしないでしょう。自社が求める人材を獲得するためにも、ジョブディスクリプションを求人情報とも連動させ、必要なスキルや業務内容を詳細に記載しましょう。
ジョブディスクリプションを求人情報にも反映することで、職務の管理が採用活動とも連動するため、一貫性のあるジョブ型雇用の運用が可能になります。求人情報にすべての職務情報を反映する必要はありませんので、求職者が求めるであろう内容を記載しておきましょう。
従業員へ職務の役割や評価基準を明確に伝える
従来の雇用形態からジョブ型雇用へ移行する際には、少なからず社内からの反発が生まれる場合があります。ジョブ型雇用自体のメリットや職務の内容、それぞれの評価基準などをわかりやすく社内へ説明しましょう。一度で理解できない場合でも、繰り返し説明を行いながら従業員の理解を促すことが重要です。ジョブ型雇用を導入したとしても、自身へのメリットや職務に求められる役割などを従業員が理解していなければ、ジョブ型雇用は形がい化してしまいます。
単にジョブディスクリプションを公開するだけでなく、その目的やメリットを伝えることが肝心です。1on1などを設けながら定期的にミーティングを実施し、継続的に伝えることで浸透を図りましょう。
ジョブ型雇用の導入企業の事例

「ジョブ型雇用」への転換の目的は企業によって異なり、その期待効果も様々です。
ここでは、ジョブ型雇用を導入している企業の事例を見てみましょう。
事例①:富士通株式会社
富士通グループは2020年にFujitsu Wayを刷新し、改革の柱としてジョブ型人事を導入しています。国内グループ企業の管理職約1万5,000人を対象に導入されたジョブ型人事は、2026年4月入社の新卒採用にもジョブを起点とした人材マネジメントに本格的にシフトする、としています。
従来の人事制度を大きく見直し、ジョブ型人事へ移行する目的として、「自律的なキャリア形成に対する社員の意識を高め、会社=組織と社員の関係性、ひいては組織文化の変革を実現するという狙いがある」と報告しています。
参考:富士通株式会社「富士通統合レポート2023」
事例②:ENEOSホールディングス
ENEOSホールディングスは「長期雇用を軸とした人材育成・自律的なキャリアの形成支援」に重点を置き、ジョブ型を導入しました。経営方針と連動させたうえで事業や職務の価値を序列化し、処遇を決定する仕組みを構築しています。
ジョブ型雇用の導入に至った背景は、以下の3つです。
- デジタル人材を含めた専門性の高い人材の採用
- 自律的なキャリア形成の支援
- 人材の最適な配置および人材活用データの管理(システム導入を含む)
管理職のみを対象(非管理職は能力等級のままで維持)とし、ポジションごとのジョブディスクリプションを作成しています。それをもとに価値を算定したうえで格付けを実施し、役職とグレードを連動させる仕組みを採用しています。
事例③:株式会社日立製作所
日立製作所は、2008年度に過去最大の赤字に計上したことから抜本的な経営再建を図り、ものづくり企業から「社会イノベーション事業」を軸としたグローバル企業へとシフトしました。約30万人の従業員数のうち約14万人が外国籍であることから、全世界の人材情報の把握、職務の明確化など、グローバルで統一された人事制度や人事プラットフォームを構築していきました。その取り組みの中で、2020年4月からジョブ型雇用・ジョブ型採用を強化し、一部の職務で学歴別の一律の初任給額ではなく、対象者のスキルや経験、職務内容などを加味した個別の処遇を設定しています。事務系職種でも「職種別採用コース」を新設しており、応募者の「就社<就職」のニーズに対応しています。
日立製作所では、全職種・全階層ごとに約450種類の「標準ジョブディスクリプション」、および全ポジションの「個別ジョブディスクリプション」を作成し、その内容を全社員に公開しています。職種(機能)×階層ごとの標準様式となる「標準ジョブディスクリプション」と、該当ポジションが特にカバーすべき領域を考慮して標準ジョブディスクリプションに追記・修正を行った「個別ジョブディスクリプション」の2種類を作成し、運用している点が特徴的です。
参考:株式会社日立製作所「日立製作所におけるジョブ型人財マネジメントと具体的施策」
事例④:ソニーグループ株式会社
ソニーグループは、2015年4月に「ジョブグレード制度」を導入し、ジョブ型の人事・等級制度を構築しています。これは「人」ではなく「現在の役割」に格付けし、公平な等級評価を行う考え方となっています。
制度の主な特徴は以下のとおりです。
- 職務評価
- 各職務の価値を客観的に評価し、グレードを決定
- グレード構成
- 職務の難易度や責任の大きさに応じて、複数のグレードを設定
- 処遇との連動
- 給与やボーナスなどの処遇がグレードと連動しており、同一グレード内では同一の処遇がを適用
ジョブグレード制度のメリットとして、以下が挙げられています。
- 公平性の向上
- 職務内容に基づく評価により、公平な処遇が実現できる
- モチベーション向上
- 能力や成果が処遇に反映されるため、従業員のモチベーション向上につながる
- 人材の流動性促進
- 職務に基づく評価により、部門間や関連会社間の人材移動が容易になる
また、運用上の留意点として、以下を挙げています。
- 定期的な職務評価の実施が必要
- 従業員への制度の十分な説明と理解促進が重要
- グレード間の移動基準を明確にし、キャリアパスを示す
このジョブグレード制度により、ソニーグループは従業員の能力と成果を適切に評価し、競争力のある人材マネジメントを実現しています。
参考:ソニーグループ株式会社「ソニーのジョブグレード制度」
事例⑤:株式会社資生堂
資生堂は、グローバルでの競争力強化と人材の最適配置を目的として、2015年に管理職を対象としたジョブグレード制度を導入し、2018年には一般社員へ対象を拡大。さらに、経営や組合との協議を経たうえで、2021年1月から正式にジョブ型人事を導入しています。
資生堂のジョブ型人事制度の特徴は以下のとおりです。
- ジョブディスクリプションの明確化
- 各職務の役割、責任、必要なスキルを明確に定義し、文書化
- グローバル共通の評価基準
- 世界中の従業員を同一の基準で評価できるシステムを構築
- 報酬制度との連動
- 職務の価値に基づいて報酬を決定する仕組みを導入
ジョブ型の主な取り組みは以下を挙げています。
- 人材データベースの構築
- 従業員のスキルや経験を可視化し、適材適所の人材配置を実現しています。
- キャリア自律の促進
- 従業員自身がキャリアを選択し、必要なスキルを習得できる環境を整備しています。
- リカレント教育の支援
- 従業員のスキルアップを支援するため、外部教育機関との連携を強化しています。
制度のメリット、期待される効果として、以下を挙げています。
- グローバル人材の育成と活用
- 組織の柔軟性と生産性の向上
- 従業員のエンゲージメント向上
制度の導入・運用における課題と対策は、以下のとおりです。
- 文化的な障壁
- 課題:日本の伝統的な雇用慣行からの転換に対する抵抗感
- 対策:丁寧な説明と段階的な導入を実施
- スキルギャップへの対応
- 課題:新たな職務要件とのギャップ
- 対策:これを埋めるため、社内外での学び直しを奨励
資生堂のジョブ型人事制度は、グローバル化と人材の最適活用を目指す同社の経営戦略と密接に結びついており、今後の企業競争力強化の鍵となることが期待されています。
参考:株式会社資生堂「ジョブ型人事制度導入を通じた資生堂の「組織変革」の方向性」
事例⑥:KDDI株式会社
KDDIは、急速に変化する通信業界においてイノベーションを促進し、従業員の成長と組織の競争力強化を目的として、ジョブ型人事制度を段階的に導入しました。まず2020年8月に中途社員を対象に適用を開始し、2021年4月に新卒社員へ適用、さらに2022年4月には非ライン管理職や非管理職まで拡大し全社員に適用しています。
KDDIのジョブ型人事制度の特徴は、以下のとおりです。
- ジョブディスクリプションの策定
- 各職務の役割、責任、必要なスキルを明確に定義し、文書化
- スキルマップの活用
- 従業員のスキルを可視化し、適材適所の人材配置を実現するためのツールを導入しています。
- 報酬制度の改革
- 職務の価値と個人の貢献度に基づいて報酬を決定する仕組みを構築しています。
主な取り組みとして、以下を実施しています。
- 社内公募制度の拡充
- 従業員が自らキャリアを選択できる機会を増やし、組織の活性化を図っています。
- リスキリングプログラムの導入
- 従業員のスキルアップを支援するため、新たな学習プログラムを提供しています。
- 評価制度の見直し
- 成果主義を強化し、職務遂行能力と実績を重視した評価システムを導入しています。
ジョブ型人事導入のメリット、期待される効果として以下を挙げています。
- 従業員の自律的なキャリア開発の促進
- 組織の柔軟性と生産性の向上
- イノベーションの創出と事業競争力の強化
制度の導入・運用における課題と対策は、以下のとおりです。
- 従業員の意識改革
- 課題:従来の年功序列的な考え方からの転換
- 対策:継続的な研修と啓発活動を実施しています。
- スキルギャップへの対応
- 課題:新たな職務要件とのギャップ
- 対策:社内外での学習機会を積極的に提供
KDDIのジョブ型人事制度は、デジタル化時代における人材戦略の核心として位置付けられており、従業員の成長と企業価値の向上を同時に実現することを目指しています。この取り組みは、日本の大手企業における人事制度改革の先進的な事例としても注目されています。
参考:KDDI株式会社「KDDI版ジョブ型人事制度 導入事例」
まとめ
ジョブ型雇用は、職務内容や必要なスキルを明確にし、その職務に適した人材を採用・配置する雇用形態です。グローバル化や専門性の高まりを背景に、富士通、ENEOS、日立製作所、ソニー、資生堂、KDDIなど、多くの大手企業で導入が進んでいます。各社とも、従業員の主体的なキャリア形成や専門性の向上、多様な人材の活躍を目指しています。
一方で、導入にはジョブディスクリプションの作成や職務定義、評価制度の見直しなど、綿密な準備が欠かせません。自社の特性を踏まえた柔軟な導入が求められるでしょう。