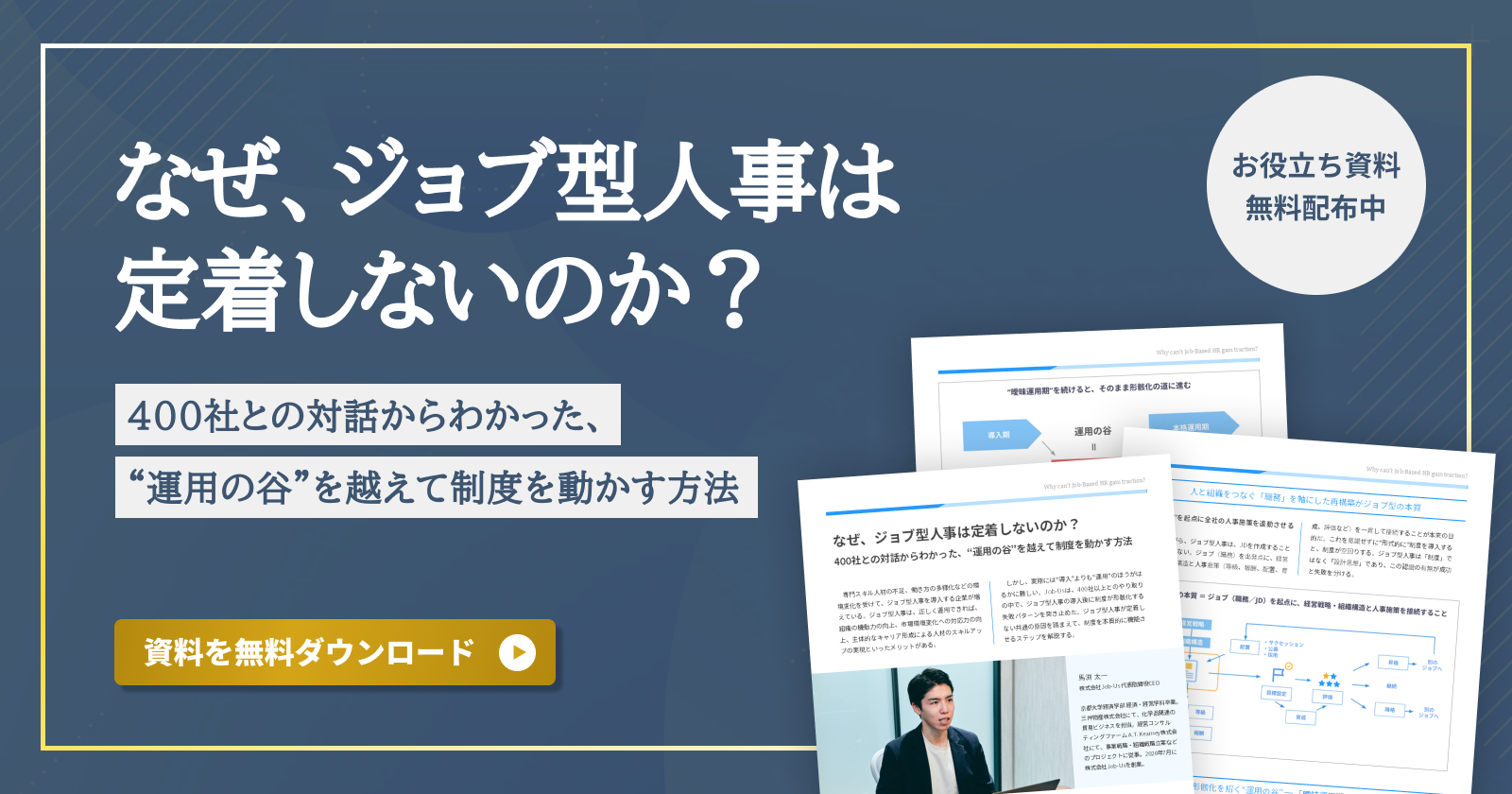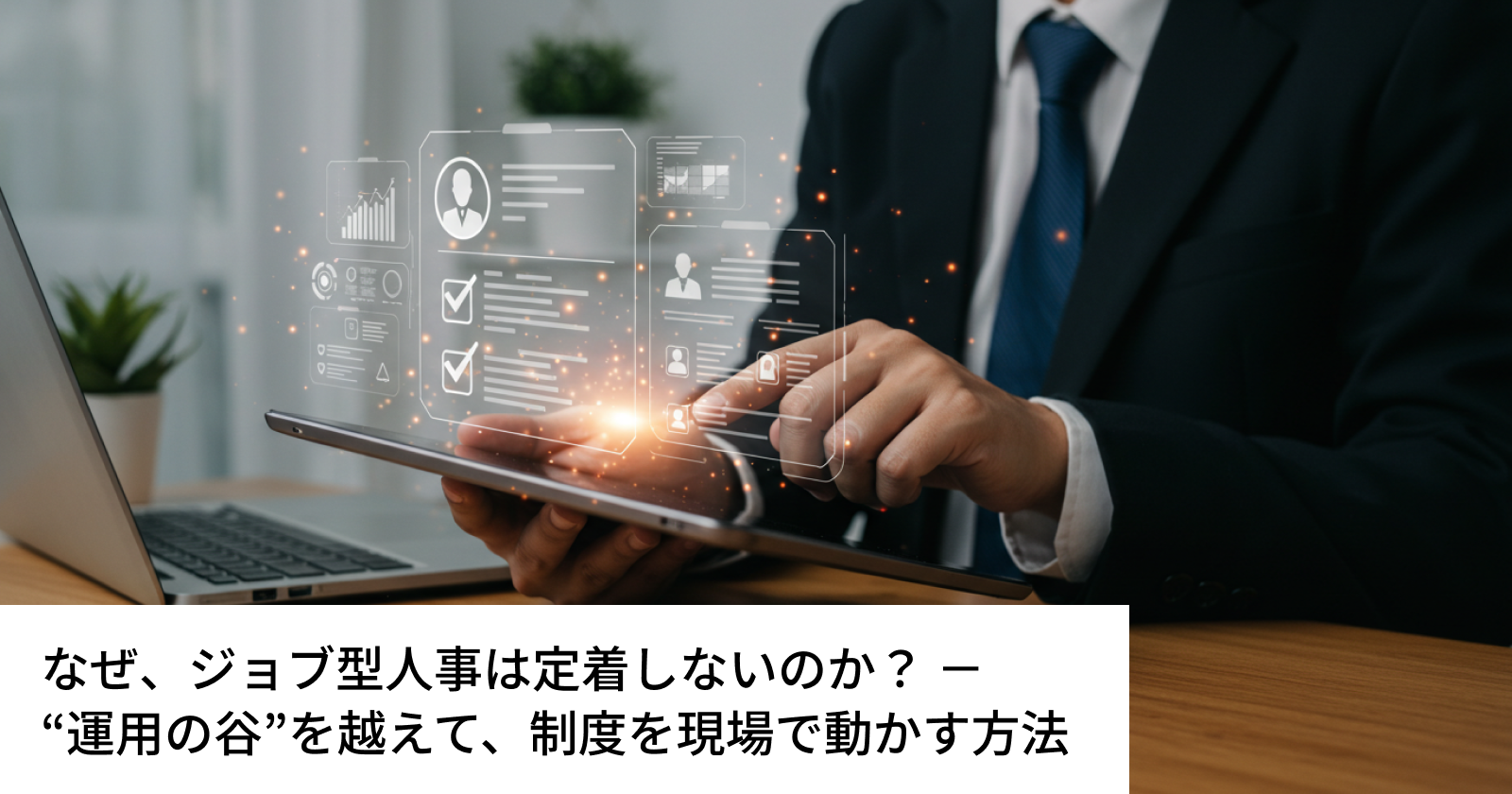ジョブディスクリプション / 職務記述書
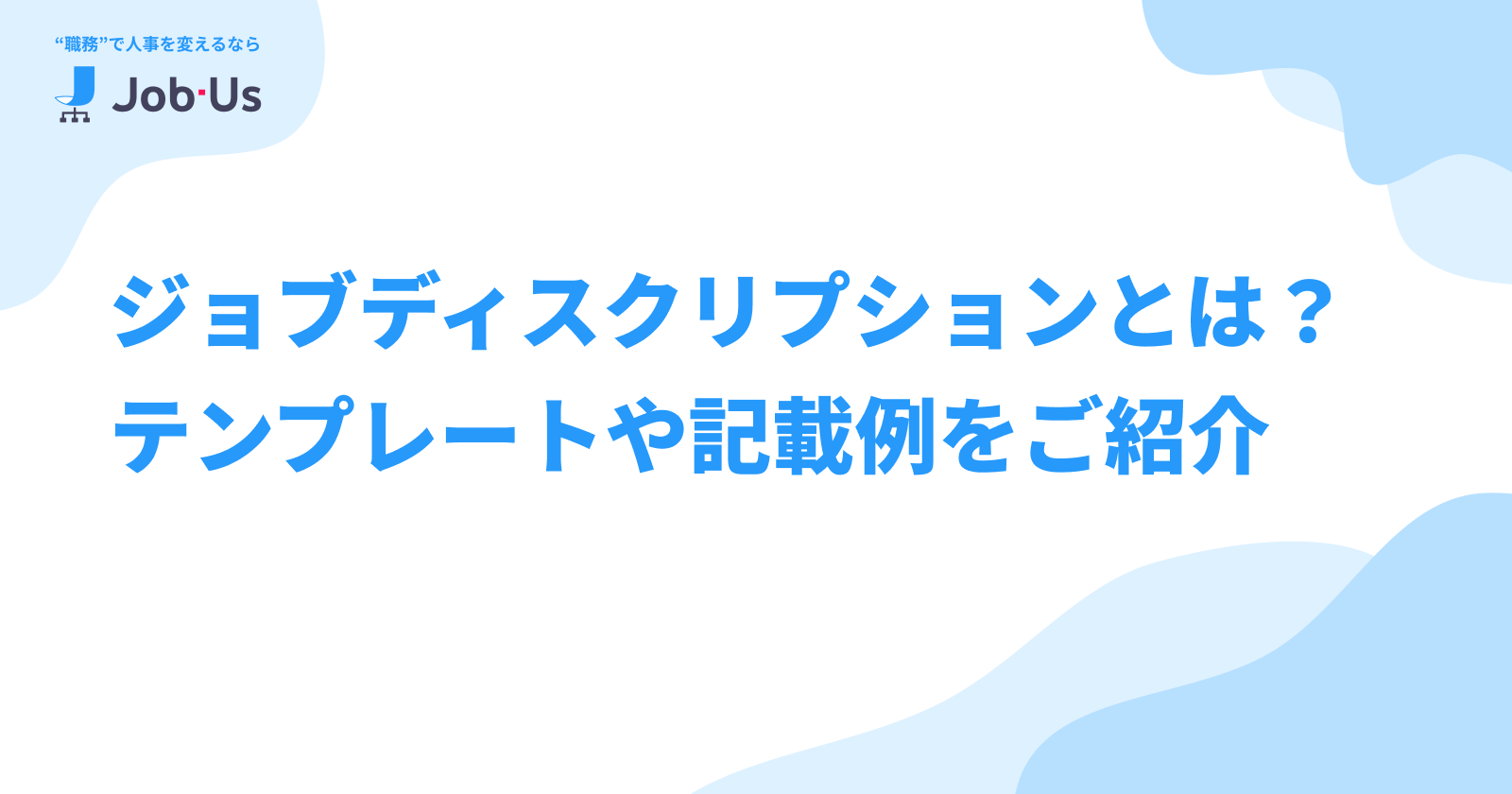
ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?テンプレートや記載例をあわせてご紹介
ジョブディスクリプション(職務記述書)が、日本企業でも注目を集めています。従来の雇用形態から「ジョブ型雇用」への移行が進む中、この文書が人事戦略の要となりつつあります。業務内容や期待される成果を明確にすることで、採用や評価の透明性が高まり、組織全体の生産性向上につながると期待されています。
本記事では、ジョブディスクリプションの概要や導入のメリット、テンプレート、記載例までを詳しく解説します。人事制度改革を検討中の企業や、キャリア開発に関心のある方は、ぜひご一読ください。
目次
ジョブディスクリプション(職務記述書)とは?

ジョブディスクリプションとは、ジョブ(職務内容)に関する詳細が記載されている文書のことです。
日本語では「職務記述書」と訳され、Job Descriptionの頭文字をとって「JD」と略称で呼ばれることもあります。
ジョブディスクリプションは、欧米で広く活用されてきた採用活動や人材評価、人材育成のための書類です。担当する仕事の詳細や範囲、必要な能力・経験、求められる成果責任などが詳しくまとめられています。
日本の会社では以前はあまり使われていませんでしたが、ジョブ型雇用や外国人採用の増加に伴い、最近注目を集めるようになってきました。
求人情報にジョブディスクリプションの内容が明確に示されると、仕事を探している人は自分のスキルや経験に合った職種を選びやすくなります。また、仕事の内容がはっきりするので、安心して職務に取り組むことができます。
「ジョブディスクリプション」が耳慣れない言葉のように感じる方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合は、転職サイトや企業の採用ページに掲載されている「求人票」を思い浮かべてください。求人票には、ジョブディスクリプションと同様の内容が記載されていることが多いため、イメージが付きやすいのではないでしょうか?
ジョブディスクリプションの目的と活用用途
ジョブディスクリプションの導入の大きな目的は、人事評価の透明性を上げ、個人や会社全体の成果を向上させることです。
ジョブディスクリプションに書かれた仕事内容や成果を達成できたかどうかで評価を行えば、より客観的で公平な評価につながります。あらかじめ仕事の内容を明確にしておくことで、本来担うべき業務がはっきりし、無駄な対立や不要な作業を減らすことができます。
具体的な活用用途としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 各役職への期待値を明確化する
- 等級の格付けや評価の根拠として活用する
- 人材開発・育成や採用促進のための文書として活用する
ジョブディスクリプションを取り入れることで、人材採用から人材開発・育成、その後の人材マネジメントまで人事領域に幅広く活用することができるのが特徴です。
ジョブディスクリプションの導入が増えている背景

日本でもジョブディスクリプションの導入が増えている理由は、「ジョブ型雇用」と密接にかかわっています。
ジョブディスクリプションは、元々「ジョブ雇用」が一般的に取り入れられてきた欧米において活用されてきました。ジョブ型雇用とは、人事制度の1つで、ジョブディスクリプションに基づく「ジョブ(職務)」を軸に、その役割・ポジションにふさわしい人材を雇う仕組みです。言わば、その職務のエキスパートを育てる雇用形態といえます。そのため、ジョブ型雇用を行う欧米企業では職務記述書が不可欠なものとして普及しています。ジョブに対して人材をあてはめていくという考え方のため、あらかじめジョブディスクリプションを作成し、そのジョブがどのような役割を担うのか、定義する必要があります。
一方、日本では従来「人」を先に採用し、そこに仕事を割り当てる「メンバーシップ型雇用」で組織を構築してきました。メンバーシップ型雇用では、定期的な異動で職務につく人材を入れ替えながら、幅広い知識を持つ人材を育成します。そのため、ジョブディスクリプションの必要性が低く、これまであまり導入されていませんでした。
しかし最近では、メンバーシップ型雇用が主流だった日本でも、ジョブ型雇用を取り入れる企業が増えています。その理由はさまざまですが、一つには個人の専門性を高めて日本の国際競争力を強化しようとする企業の狙いがあります。
また、ITスキルを持つ専門性の高い人材の不足や、多様性経営に基づく外国人雇用の増加、多様な価値観を持つ社員の増加、リモートワークの浸透、転職市場の活性化などにより、ジョブディスクリプションをもとに各ジョブの内容を明確に定め、求職者や社員1人1人に期待値を伝える必要性が高まっています。さらに、同じ仕事なら同じ待遇が求められる「同一労働同一賃金」の導入も、ジョブ型雇用を後押しする要因となっています。
そのような経緯から、ジョブ型人事制度を導入する企業も増えてきました。一方で、いざジョブ型を導入するとなると、人事制度を抜本的に改革しなければならないことが多く、足踏みしてしまう企業や、数年単位の長い期間をかけてジョブ型へ移行していく企業も少なからず存在しています。
そのため、ジョブ型の制度自体は導入せず、ジョブディスクリプションをまず導入して、求人情報に活用したり社員それぞれとジョブの期待値をすり合わせする企業もあります。
日本企業のジョブ型雇用導入例
日本においては、大企業を中心にジョブ型雇用とジョブディスクリプションの導入が進んでいます。
- 富士通
- 2015年から一部の上級管理職向けに導入。ジョブ・ポジションを世界基準で7段階に分け、報酬を連動させる「FUJITSU Level」を採用。2020年度に管理職1万5,000人へ拡大し、その後一般社員にも広げている。
- ENEOSホールディングス
- 「長期雇用を軸とした人材育成・自律的なキャリアの形成支援」に重点を置き、ジョブ型を導入。経営方針と連動させたうえで事業や職務の価値を序列化し、処遇を決定する仕組みを構築。
- 日立製作所
- 全社的にジョブ型雇用を拡大し、全職種のジョブディスクリプション標準版を作成。2021年度以降、本格的な運用を開始している。
ジョブディスクリプション導入のメリット

採用や人事評価にジョブディスクリプションを活用することで、どのような効果が期待できるのでしょうか。
ジョブディスクリプションを導入するメリットを6つご紹介します。
- 業務範囲と給与が明確になる
- 人事評価の公平性が高まる
- スペシャリストを育成できる
- キャリアパスの指針が明確になる
- 採用時のミスマッチが減る
- 生産性向上や効率化につながる
業務範囲と給与が明確になる
欧米企業でよく見られる、ジョブディスクリプションをもとにした評価の仕組みを「職務等級制度」と呼びます。この制度では、仕事内容と報酬が直結するため、雇用側と従業員の双方にとって給与体系や報酬面との連動性が明確に理解しやすくなります。
そのため、公平な評価がしやすく、従業員からの不満や不安も出にくいと考えられています。
日本企業では「総合職」として一括採用するなど、職務内容が明確でないことも多く、必要に応じて際限なく業務が増えてしまう可能性があります。新たな仕事のために残業が必要になることも考えられます。
こうした業務量のばらつきをなくし、給与体系を分かりやすくするには、ジョブディスクリプションの導入が効果的です。
人事評価の公平性が高まる
ジョブディスクリプションは「人事評価の明確な基準」として活用できます。人事評価には「評価制度」「等級制度」「報酬制度」の要素があり、ジョブディスクリプションではこの3つをすべて連動させることが可能です。
具体的な業務内容や目標をあらかじめ設定しておくことで、そのポジションに求められる期待値と現状の成果を比較しやすくなります。また、客観的な評価基準ができることで「評価の効率化」だけでなく、誰が評価しても同じ結果が得られる「公平性」も生まれます。
さらに、評価の主観的な要素が減ることで、従業員の評価に対する納得度も高まるでしょう。
スペシャリストを育成できる
ジョブディスクリプションに基づく雇用は、その仕事に適した人材の採用や、ジョブに合わせた能力開発を基本としています。また、通常は異動がないため、一つの職務でより深く技能を磨くことができます。
そのため、特定の分野や技能に特化したスペシャリスト型の人材を育てられるというメリットが期待できるでしょう。
キャリアパスの指針が明確になる
一般的にジョブディスクリプションは社内に広く公開されます。そのため、現在のポジションから上位のジョブ・ポジションに進むためにどのようなスキル・能力が必要になるかを確認することが可能です。
上位ジョブに求められる要素が明確になるため、キャリアパスとしてどのような経験を積むべきか、どのようなスキルを身につけるべきかがわかりやすくなります。
また、上位ジョブへの成長だけでなく、社内でのキャリアチェンジの指針にもなります。社内の他職種のジョブディスクリプションを確認することで、キャリアチェンジをするためにはどのようなスキル・能力を習得する必要があるかを理解することが可能です。
採用時のミスマッチが減る
事業を成長させるには、自社に合った人材の採用が欠かせません。しかし、どんな人材が必要かを定義するのは意外と難しく、あいまいになりがちです。
ジョブディスクリプションを活用すれば、必要な技能や業務遂行能力など様々な面から客観的に判断できるため、採用したい人物像をより明確にできます。これにより、応募者の選考や転職希望者とのマッチングが効率化されるでしょう。
さらに、転職希望者側も応募段階で詳しい職務内容がわかるため、入社前後のイメージのずれを防ぎやすくなります。ジョブディスクリプションを活用することで、予想外のミスマッチを防ぎ、早期退職リスクの低減も期待できます。
生産性向上や効率化につながる
ジョブディスクリプションに基づく雇用では、その仕事に必要な能力や特性を持つ人材を配置することが基本です。そのため、従来のように育成に大きなコストをかけずに済み、最小限の費用で最大限の成果を出せる適材適所の人員配置が可能になります。
また、ジョブディスクリプションでは、それぞれの仕事ごとに業務内容や達成すべき目標を詳しく定めるため、従業員は「自分のやるべきこと」をより深く理解できます。同時に、「誰がすべきか不明確なので何となく行う」「手が空いていそうだから頼む」といった、あいまいな業務の割り当ても減らすことが可能です。
さらに、ジョブディスクリプションにより勤務地や時間を限定することで、様々な形で人材を雇用することも可能になります。個々の生活状況により、能力はあるが正社員として働けない人材を有効に活用し、組織の生産性向上につなげることも期待できます。
ジョブディスクリプションのデメリット

次に、職務記述書を導入することによるデメリットを説明します。
作成・管理に手間がかかる
ジョブディスクリプションを導入する場合、社内のポジション1つ1つに対してジョブディスクリプションを作成する必要があります。企業規模が大きい場合や職務が細分化されている場合には、作成するジョブディスクリプションの数が膨大になり、大きな工数がかかります。
また、一度作成したら終わりではなく、組織や市場環境の変化に応じて定期的に見直し、アップデートしなければなりません。ポジションの数が多いと、該当ジョブのジョブディスクリプションはいつ作成されたのか?どのジョブディスクリプションが更新されていないのか?といった管理も大変です。
さらに、ジョブディスクリプションは、該当ジョブの上司が作成することが一般的となっているため、ジョブディスクリプションの作成方法に関するガイダンスも各部署に説明し理解してもらう必要があります。
仕事の柔軟性が失われる
職務内容が明確に定められているため、人によっては「ジョブディスクリプションに記載のある仕事さえすれば良い」ととらえ、記載がない仕事を担わなくなるリスクがあります。「これは自分の仕事ではない」「自分の仕事以外はしなくてもよい」という意識・考え方が生まれる場合があり、誰も担わない仕事が出てきたり、業務の押し付け合いが起こるケースもあり得ます。
従業員がこうした考え方を持ち始めたり、ジョブディスクリプションで記載された仕事しかしないような傾向が出た際には、企業は人事戦略や経営方針そのものを変更していく必要があります。該当の社員との密なコミュニケーションや意識の補正をしなければならず、場合によっては従業員の退職につながることもあるでしょう。
ゼネラリストの育成が困難
ジョブディスクリプションは、業務内容を明確に定義するため仕事を特定の領域に絞っていくことになります。ジョブディスクリプションに定められた領域の業務に特化して経験を積み、専門領域のスキルやキャリアを伸ばしていくためには適した仕組みとなりますが、幅広い領域の仕事を経験するためには向いていません。
したがって、ゼネラリストを育成するためにはあまり向いていないと言えます。
スペシャリストが増えすぎると、組織の柔軟性が低下する恐れがあるため、経営や事業成長において幅広い分野を広く浅く理解し経験しているゼネラリスト人材も欠かせません。ジョブディスクリプションを導入する際には、「ゼネラリストの育成」も考慮した設計が必要になります。ジョブローテーションや社内でのキャリアチェンジなどを含めて、人事制度全体を包括して設計していくことが重要です。
ジョブディスクリプションの作成方法

ジョブディスクリプションの目的は「個人や会社全体の成果を向上させること」です。ジョブ型を正しく導入するためには、ジョブディスクリプションと経営戦略との連動が不可欠です。いきなりジョブディスクリプションの作成にとりかかるのではなく、以下のステップに沿って作成を進めましょう。
ステップ1・2を先に整理・理解しておくことで、ステップ3で作成するジョブディスクリプションと経営戦略を接続させることが可能です。
- ステップ1
- 経営・事業戦略と組織ごとに求められる役割を理解する
- ステップ2
- 組織内の各ポジションの役割と責任範囲を明確化する
- ステップ3
- 実際にジョブディスクリプションを作成する
各ステップを具体的にご説明します。
ステップ1:経営・事業戦略と組織ごとに求められる役割を整理する
ジョブ型人事・ジョブディスクリプションの導入目的は「個人や会社全体の成果を向上させること」です。そのため、ジョブ型人事制度を正しく機能させるためには、ジョブディスクリプションが経営戦略・事業戦略と連動していることが不可欠です。
まずは、会社の経営・事業戦略を理解し、それに紐づいた組織ごとに求められる役割を整理します。
ステップ2:組織内の各ポジションの役割と責任範囲を明確化する
ジョブディスクリプションを作成するそれぞれの職務の情報を集め、各ジョブの職務等級、責任、仕事内容、必要な知識やスキル、求められる責任範囲などを明確にします。実情を理解するためにも、職務ごとに該当の業務を実際に行っている従業員へのヒアリングを実施しましょう。
現場スタッフの声を聞くことで、会社が求めている役割と現場での行動のズレを最小限に抑えることができます。情報の偏りをなくすために、各ジョブごとに複数の従業員から意見を聞くのが望ましいです。
次に、集めた情報を人事部門や部門責任者を中心に精査します。職務を遂行するために必要な業務内容を一つずつ定義し、「何を目的に(Why)」「誰が(Who)」「どのような業務を(What)」「どのように実施するか(How)」を整理していきましょう。
- 何を目的に(Why)
- 誰が(Who)
- どのような業務を(What)
- どのように実施するか(How)
ステップ3:実際にジョブディスクリプションを作成する
ステップ1・2で整理した情報をもとに、各ジョブの内容を記載したジョブディスクリプションを作成していきます。次でご紹介するジョブディスクリプションの記載項目やテンプレートを参考に作成してみましょう。
作成が完了したら、後ほど解説する「ジョブディスクリプション導入時の注意点」を意識して、運用していきます。
ジョブディスクリプションの記載項目

ジョブディスクリプションには統一されたフォーマット等はありませんが、そのジョブのミッションや責任範囲、期待される役割、ジョブを遂行するにあたって必要なスキルなどを記述するのが一般的です。
以下のような項目を記載します。
- ポジション名
- 該当ポジションの名称を記載します
- 現職者氏名
- 実際に該当ポジションについている方の名前を記載します(人材育成用途でジョブディスクリプションを作成する場合は、空欄のままにします)
- レポート先
- 該当ポジションの上司にあたるポジションを記載します
- 部下人数
- 目安としてどのくらいの人数を部下とするか記載します
- 組織図
- 該当ポジションが組織図のどこに位置するかを記載します
- ミッション
- 該当ポジションが担う任務を記載します
- 期待される成果責任
- 該当ポジションの主な業務内容を記載します
- 求められるKPI
- 該当ポジションで求められる成果指標を記載します
- 求められる経験
- 該当ポジション就任において必要な経験を記載します
- 求められる能力・知識
- 該当ポジション就任において必要な能力や知識を記載します
- 求められるコンピテンシー
- 該当ポジション就任において必要な行動特性を記載します
これらの項目を適切に記載することで、応募者や従業員は職務内容や期待される役割をより明確に理解できるようになります。
ジョブディスクリプションのテンプレート

Job-Usが独自に作成したジョブディスクリプションのテンプレートをご用意しました。スプレッドシートのテンプレートになりますので、以下のリンクからコピーしてご利用ください。
▼ジョブディスクリプションのテンプレートはこちら
ジョブディスクリプションテンプレート(Spreadsheet)
ジョブディスクリプションの記載例
テンプレートの記載例として、「営業部の課長」職の場合の例をご紹介します。

営業職のジョブディスクリプションを作成する際は、担当エリアや営業手法などの職務詳細や、「新規開拓数〇件」などの具体的なKPIを明記しましょう。
ジョブディスクリプション導入時の注意点

ジョブ型人事を効果的に運用するため、ジョブディスクリプションの導入時に意識しておきたい注意点を紹介します。
上下および横の職務と比較・確認をする
例えば、営業部長と営業メンバーの期待役割に「重要顧客との関係構築」と書かれており、営業課長の期待役割には書かれていない場合、組織で戦略の整合性が取れていないことになります。
また、同様に他の「課長」職には人材育成に関する期待役割が書かれているにもかかわらず、営業課長にだけ書かれていなければ整合性が取れません。
したがって、上下のみならず横並びでジョブディスクリプションを比較・確認することが重要です。
公開範囲を明確化する
全社員に対して全てのジョブディスクリプションを開示するケースもあれば、ある役職以上のみに開示するケース、所属組織内のみに開示するケースなどがあります。
自社のジョブディスクリプションの開示範囲を明確化し、どの項目までを公開するかも併せて設定しましょう。
定期的な更新・メンテナンスを行う
ジョブディスクリプションは一回作ったら終わりではなく、定期的なメンテナンスが必要です。主に、以下4つのタイミングで定期的に見直し、更新を実施しましょう。
- 組織再編のタイミング
- 異動のタイミング
- 半年または一年ごとの定期見直し
- 中期経営計画策定のタイミング
事業戦略や市場環境の変化に応じて内容をアップデートすることで、ジョブディスクリプションの記載内容と実際の業務内容にズレが生じることを防ぐことができます。
まとめ
ジョブディスクリプションは、職務内容を詳細に記した文書です。欧米で広く活用されてきましたが、近年日本企業でも注目を集めています。主な目的は、人事評価の透明性向上と成果の向上です。業務範囲と給与の明確化、公平な評価、スペシャリスト育成、キャリアパスの明確化などのメリットがあります。
一方で、作成・管理の手間や柔軟性の低下といったデメリットもあります。導入時には経営戦略との連動や定期的な更新が不可欠です。ジョブ型雇用の増加に伴い、今後さらに重要性が高まると言えるでしょう。