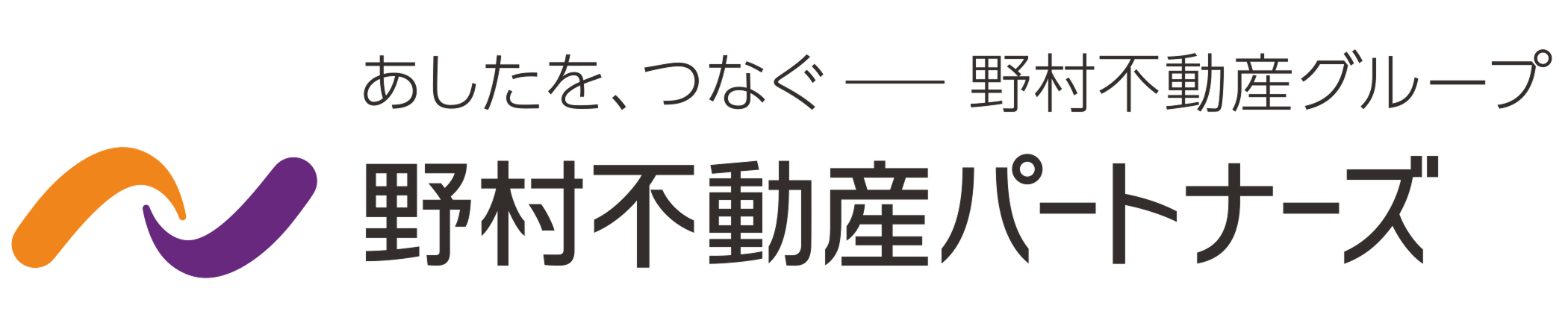ジョブディスクリプションを基盤として、「人ありき」から「ジョブありき」の人材戦略に転換
食品・飲料
500~999人
- AIアシスタントJD作成
- 職務評価
導入企業
| 社名 | ナッシュ株式会社 |
| 従業員数 | 500名(連結) |
| コーポレートサイト | https://nosh.jp/company |
課題と導入効果
| 課題 |
|
| 解決策 |
|
| 導入効果 |
|
ナッシュ株式会社(以下、ナッシュ)は、2016年設立のベンチャー企業。「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションの達成を目指して、生活習慣病予防に貢献するため、低糖質・低塩分をコンセプトとした自社製造の冷凍宅配弁当「ナッシュ(nosh)」を提供しています。
同社は、 ジョブ型人事制度を推進するにあたり「Job-Us」を導入。Job-Usカスタマーサクセスチームのサポートのもと、約1ヶ月で150のジョブディスクリプション(以下、JD)を作成し、ジョブ型人事運用の基盤を整えました。
「Job-Us」導入の決め手や目指す組織像、そして、その実現に向けた「Job-Us」の活用法について、経営本部 人事部 部長の門田さんと人事部 人事課の山下さんにお話を伺いました。
求めたのは、JDの作成から管理・運用まで一貫して行えるシステム
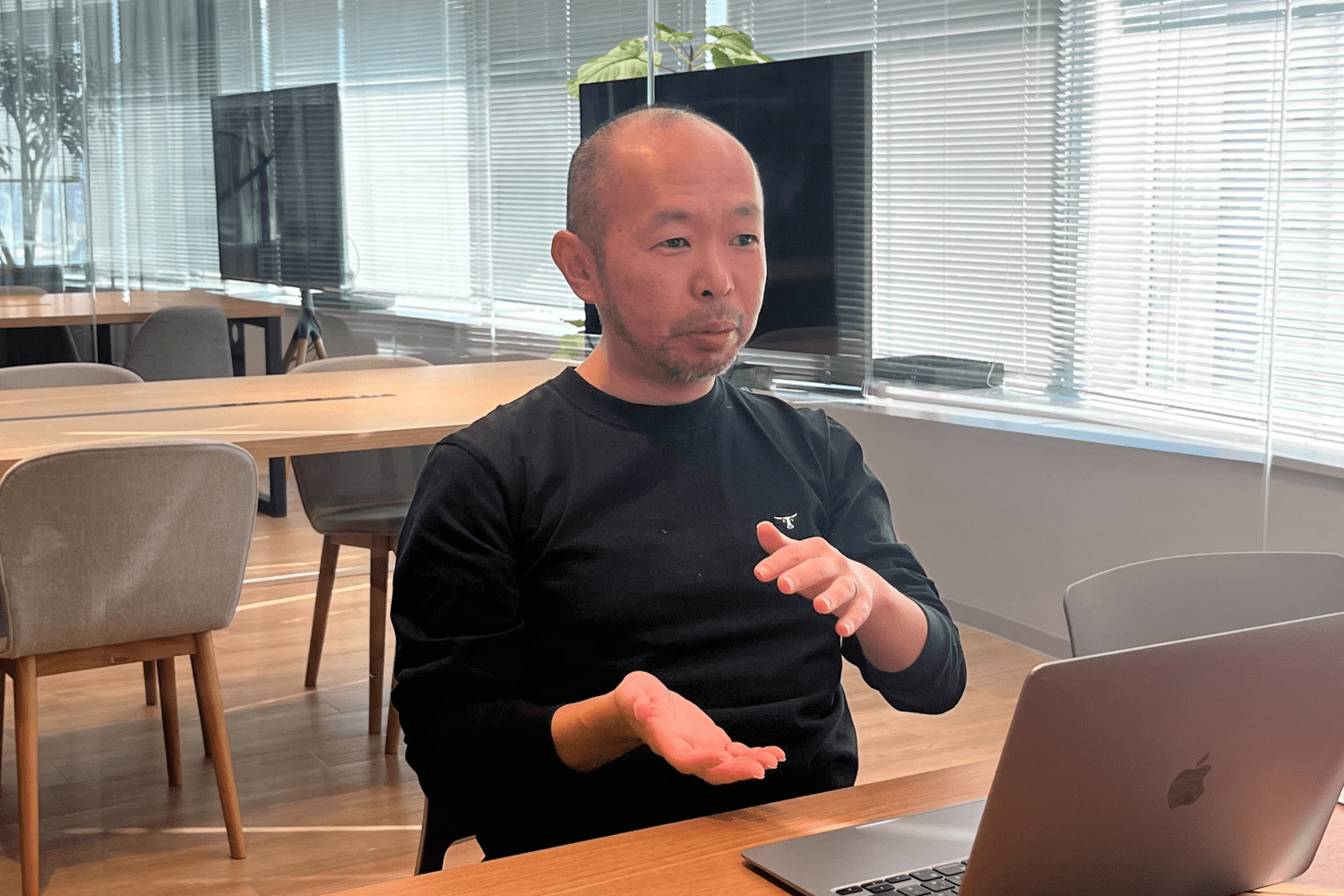
経営本部 人事部 部長 門田さん
―ジョブ型人事制度を導入した経緯を教えてください。
門田さん:事業成長に伴って従業員が急速に増えていく中、個々人の役割を明確に規定すべく、 当社の実情に適したジョブ型人事制度を導入することにしました。
当社はもともとウェブマーケティングを主業としており、エンジニアやウェブマーケターなど、職種ごとの役割が明確な専門職が多いのが特徴です。業務もプロジェクト単位で進められることが多く、すでにジョブ型に近い働き方が浸透しています。KPIマネジメントも行っているので、社員のジョブに対する理解も早いはず。こうした背景から、当社はジョブ型人事制度との親和性が高く、スムーズに導入できると判断しました。
今回の人事制度見直しは、人事の領域を超えた経営戦略そのものに関わる取り組みです。そのため、私や山下が所属する人事部が経営本部に加わり、経営本部が主導する部門統制プロジェクトの一環として進めています。
—ジョブ型人事を導入しても、JDを作成しないケースもあります。ナッシュ様がJDを作成した目的を教えていただけますか?
門田さん:ジョブ型でもメンバーシップ型でも、どのような人事制度を取り入れるにせよ、自社のすべてのジョブを可視化し、明確に定義することは必要不可欠だと考えています。当社にはこれまでJDが存在していなかったので、まずはJDを作成し、それをもとに職務を公平かつクリアに評価する新しい評価制度の構築を目指しました。
ただ、ナッシュ全体のJDを作成するとなると、非常に大きな労力を要します。社内で対応するのはとても不可能だろうということで、さまざまな作成支援ツールを探し、「Job-Us」にたどり着きました。
—複数の選択肢がある中から、「Job-Us」を選定した決め手は何だったのでしょうか?
門田さん:私たちは今後、JDが経営の基盤になると考えています。今回のプロジェクトでJDを作成して終わりではなく、社内でJDの作成から管理・運用まで一貫して行えるシステムが必要です。そうした私たちのニーズをしっかりと満たしているのが「Job-Us」でした。JDの運用に必要な機能がこれほど充実しているシステムは、他に見当たりません。
私たちは「Job-Us」に対し、ジョブ型人事の本質を捉えたシステムという印象を持っています。「JDを基盤に組織を発展させる」というプロダクトのビジョンが感じられ、それが私たちの目指す方向性と一致していたことが、導入の決め手となりました。
また、Job-Usカスタマーサクセスチームにはジョブ型人事に関する深い知見があり、その知見を活用できることも、当社の大きな強みになると考えました。
JDを社員のジョブ型人事に対する理解促進ツールに
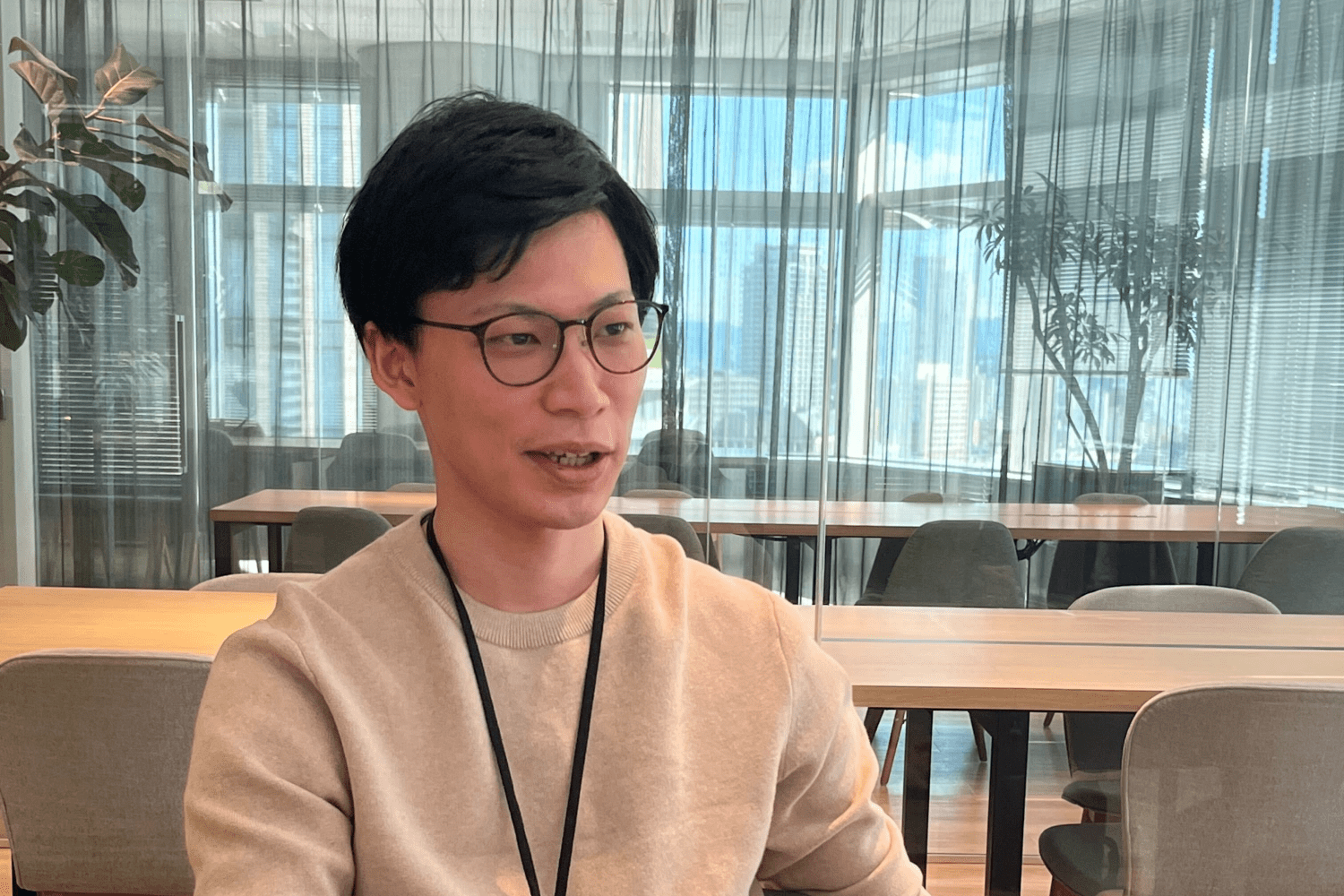
経営本部 人事部 人事課 山下さん
―「Job-Us」導入後、JDの作成はスムーズに進みましたか?
山下さん:Job-Usカスタマーサクセスチームに伴走支援してもらい、1ヶ月で150のJDを作成できました。作成の流れは、まず人事部とJob-Usカスタマーサクセスチームが協力してAI機能を使ってJDのドラフトを作成し、各本部長が内容を確認。そのフィードバックをもとにJob-Usカスタマーサクセスチームがドラフトを修正し、最後に人事部が最終調整して完成に至る、というものです。
1ヶ月というスピード、JDのクオリティーともに、非常に満足しています。社内で、それも人力で作成していたら、とてもこうはいかなかったでしょう。
―今後、JDをどのように活用していくのでしょうか?
門田さん:2023年から準備してきた新しい評価制度もようやく整い、2024年12月にいよいよジョブ型人事制度への移行を始めます 。今後はJDを基盤として、経営戦略と連動した人材戦略を実践していきます。
具体的には、経営戦略に基づいて組織を編成し、組織が果たすべきミッションを遂行するために必要なジョブを定義。そのうえでジョブに最適な人材を配置することで、環境変化に応じて戦略を立案し、戦略に合わせて組織を柔軟に編成できる体制を目指しています。要は、従来の「人ありき」の発想から、「経営戦略・ジョブありき」への転換です。これこそが本来のジョブ型人事制度であり、私たちが目指す組織像です。そして、組織設計、組織運営の基盤となるのがJDです。
―そこまで徹底したジョブ型人事を実践する企業は、日本ではなかなかありませんね。
門田さん:おそらくそうだと思います。実際、完全なジョブ型に移行するのは容易ではありませんから。ただ、メンバーシップ型と併用するような不完全な取り入れ方は、現状維持のための妥協策にすぎず、かえってジョブ型人事制度への理解 を阻害しかねません。ジョブ型を導入するからには、徹底的に取り組むべきというのが私たちの考えです。
―ジョブ型に移行するにあたり、最も大きな課題は何でしょうか?
山下さん:社員の評価方法や組織のあり方が大きく変わる中、社員のジョブ型に対する理解をいかに促していくか。これが一番の課題ですね。
その際にJDは、社員の意識変革を進める有効なツールになると考えています。経営戦略と連携するJDを提示することで、社員一人ひとりが自分の役割や責任を理解し、会社の目標達成に向けてモチベーション高く取り組めるようになります。ジョブ型人事制度の効果が発揮され、組織全体のパフォーマンス向上につながると考えています。
豊富なジョブデータベースを人的資源管理に活かす
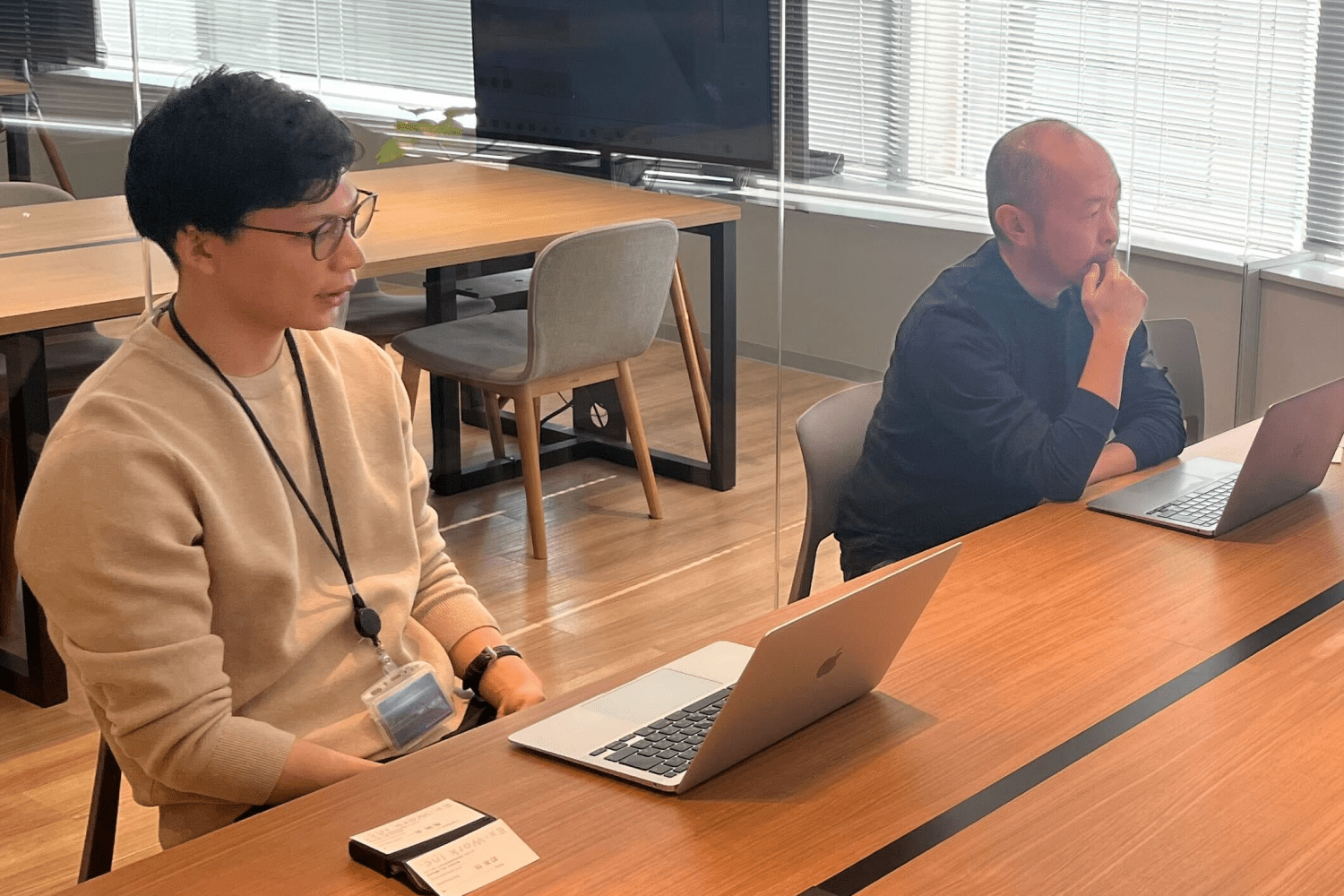
―今後、ジョブ型人事制度を推進していくうえで、「Job-Us」をどのように活用していきたいですか?
山下さん:まずは、ジョブ型人事を社員に周知する場で“理解促進ツール”として活用したいです。
また、今後は職務評価の導入を予定しています。想定しているのは、職務と職位を組み合わせてジョブサイズを評価し、それをもとに人件費を管理する仕組みです。たとえば「人事部の各ジョブのジョブサイズを合算し、人事部全体のジョブサイズから人件費を算定する」というように、組織単位のジョブサイズを算定し、組織のジョブサイズに連動した人件費管理をしたいんです。こうした管理も「Job-Us」を使って効率的に進めていきたいですね。
門田さん:「Job-Us」の豊富なジョブデータベースを活用できるのも、このシステムを使う大きなメリットです。汎用的なジョブ情報が網羅されているので、自社だけでなく他社にはどんなジョブがあるのかも知ることができます。他社との比較を通じて、自社に不足しているジョブや見直すべきジョブを把握し、ジョブの最適化を図る、といった使い方もできるかと。将来必要となるジョブの予測にも役立ち、採用戦略や人材育成をより効果的に進められると期待しています。
―最後に、今後の展望をお聞かせください。
門田さん:これまで日本の企業では「人ありき」の人事運営が当たり前で、「人を起点としない」人的資源管理・人的資本経営を実現している企業はほとんどありません。そんな中、私たちは、経営戦略と人材戦略が一体化した本来の「人的資本経営」を事業会社として確立したい。前例がないからこそ、自分たちが「こんな人事運営もできるんだ」という好例を示したいですね。
※掲載内容は、2024年11月の取材時点のものです。